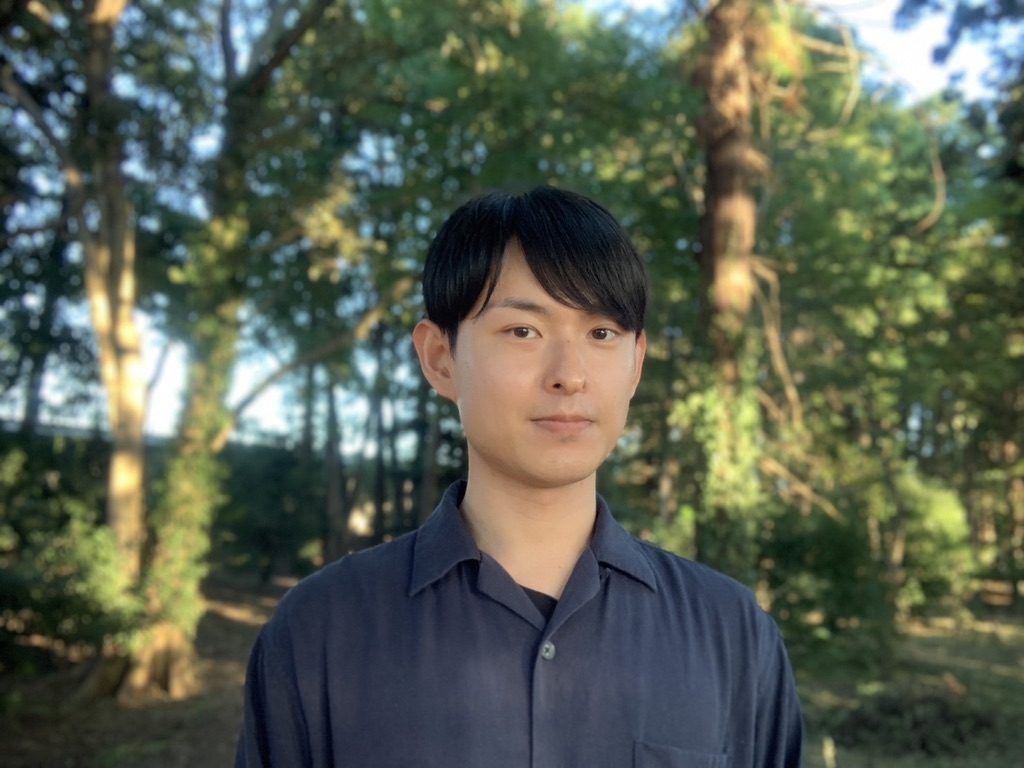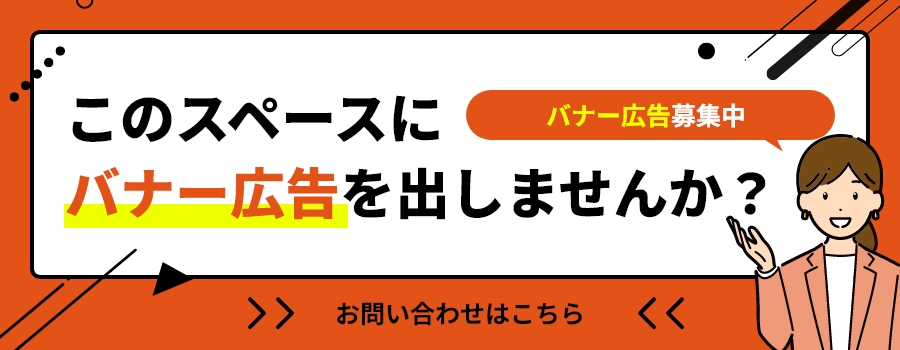記事監修者:内藤かいせい 先生
運動時に膝の外側に痛みが現れた場合、それは腸脛靱帯炎の可能性があります。腸脛靭帯炎を疑ったときに、どのような症状が現れるのか、どんな方法でチェックできるのか知りたい方もいるのではないでしょうか。
この記事では、腸脛靭帯炎の症状やセルフチェック方法、治療法をご紹介します。この疾患の知識を深めることで、早期からの対処ができるようになるでしょう。
腸脛靭帯炎(ランナー膝)とは?
腸脛靭帯炎とは、腸脛靭帯(ちょうけいじんたい)と呼ばれる、太ももの外側につく靭帯に炎症が起こる疾患です。ここでは、腸脛靭帯炎の具体的な症状や原因を解説します。
腸脛靭帯炎のおもな症状
腸脛靭帯炎の代表的な症状は、運動時の膝外側の痛みです。腸脛靭帯と大腿骨(だいたいこつ:太ももの骨)の出っ張った部分が繰り返し擦れることで炎症を起こし、痛みとして現れます1)。ランニングで腸脛靭帯炎が起きやすいことから、「ランナー膝」とも呼ばれます。
腸脛靭帯炎の初期段階では、安静にすれば症状は落ち着きますが、運動を再開すると痛みが再発するのが特徴です。重症化すると安静時にも強い痛みを感じることもあるため、早期からの対処が重要です。
腸脛靭帯炎の発症原因
腸脛靭帯炎の発症原因は、おもに運動が関係しています。具体的な要因としては、以下のとおりです。
- 運動のしすぎ
- 練習環境の変化
- 運動靴の変更
- 運動環境(硬い路面や傾斜のある道路など)
そのほかの要因として、生まれつき大腿骨の出っ張り部分が大きい場合や、O脚(足がOの字のようになっていること)などがあげられます1)。
腸脛靭帯炎の症状をセルフチェックする方法
腸脛靭帯炎かどうかをセルフチェックするポイントとして、以下の痛みの有無を確認します。
- 運動時の膝外側の痛み
- 圧痛(押したときの痛み)
まず、運動時に膝の外側に痛みを感じるかどうかを確認してみてください。次に、膝を軽く曲げた状態で、膝関節の外側から少し上の部分を親指で押してみましょう。この部分には腸脛靭帯があり、押したときに痛みを感じる場合は、腸脛靭帯炎の可能性があります1)。ただし、セルフチェックはあくまで目安であり、正しい診断には整形外科の医療機関への受診が必要です。
腸脛靭帯炎に類似した疾患
膝まわりの痛みの原因は腸脛靭帯炎だけでなく、場合によってはほかの疾患を発症している可能性もあります。ここでは、腸脛靭帯炎に類似した疾患をご紹介します。
鵞足炎
鵞足炎(がそくえん)とは、膝の内側に位置する「鵞足」と言う部分に炎症が起こる疾患です。鵞足とは、股関節や膝の動きに関係する筋肉の腱が集まる部位のことです。鵞足炎を発症すると、運動時に膝の内側下方の痛みが現れます2)。
鵞足炎が発症する原因は、繰り返しの膝の曲げ伸ばし、急激な膝への負荷の増加などがあげられます。腸脛靭帯炎と同じように、ランニングやサッカーなどのスポーツでみられやすいのも特徴です。
膝蓋腱炎(ジャンパー膝)
膝蓋腱炎(しつがいけんえん)とは、膝のお皿の下にある「膝蓋腱」に炎症が起こる疾患です。名前のとおり、バレーボールやバスケットボールなどのジャンプや着地動作を繰り返すスポーツで発症します3)。
ジャンパー膝のおもな症状は、運動時に現れる膝前面の痛みです。とくにジャンプや階段を上る動作で痛みが強くなる傾向にあります。この疾患が起こる原因として、太ももの筋肉である「大腿四頭筋(だいたいしとうきん)」の過度な収縮による膝蓋腱へのストレスがあげられます。
膝靭帯損傷
膝靭帯損傷(ひざじんたいそんしょう)とは、膝関節の安定性を保つ靭帯が損傷する疾患です。膝には以下の4つの主要な靭帯があり、それぞれが膝の動きを制御して関節の安定性を高めています4)。
- 前十字靭帯(ぜんじゅうじじんたい):膝関節内にある靭帯
- 後十字靭帯(こうじゅうじじんたい):膝関節内にある靭帯
- 内側側副靭帯(ないそくそくふくじんたい):膝関節の内側にある靭帯
- 外側側副靭帯(がいそくそくふくじんたい):膝関節の外側にある靭帯
靭帯損傷の原因は運動によるものが多く、スポーツ中の急な方向転換や着地時の衝撃などがあげられます。膝靭帯損傷を発症すると、激しい痛みや腫れなどが現れ、重度の場合は歩行が難しくなることもあるでしょう。
膝靭帯の特徴や損傷時の対処法について知りたい方は、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:【医師監修】膝靱帯の痛みがあるときの対処法は?代表的な疾患や治療法を解説
腸脛靭帯炎の治療内容
腸脛靭帯炎を発症した場合、どのような治療が行われるのでしょうか。ここでは、腸脛靭帯炎の具体的な治療内容について解説します。
【発症直後】安静・患部のアイシング
腸脛靭帯炎の発症直後は、安静と患部のアイシングによる処置が行われます1)。まずは患部に負担をかける運動を中止し、安静を優先します。ランニングやジャンプなど膝の曲げ伸ばしをともなう動作は避け、痛みがある間は無理に動かさないようにしましょう。
アイシングについては、氷水や保冷剤を使って患部を冷やします。アイシングによって血管を収縮させ、炎症の拡大を防ぐとともに痛みをやわらげます。
【痛みが落ち着いた時期①】下半身のストレッチ
痛みが落ち着いた時期では、下半身のストレッチで筋肉の柔軟性を高めることが重要です1)。筋肉の柔軟性を高めることで腸脛靭帯の摩擦が軽減し、症状の改善が期待できます。下半身の筋肉のストレッチ方法は以下のとおりです。
【大腿筋膜張筋のストレッチ方法】
- あお向けになって片膝を曲げる
- 曲げた膝の上に反対の足を乗せる
- 乗せた足の方向に身体をひねる
- 身体をひねった状態を20秒ほどキープする
- 反対の足で行う
このストレッチでは、股関節の外側にある腸脛靱帯とつながっている「大腿筋膜張筋(だいたいきんまくちょうきん)」と言う筋肉を伸ばせます。
【痛みが落ち着いた時期②】筋力トレーニング
ストレッチと同時に、下半身の筋力トレーニングも並行して行います1)。筋力トレーニングによって股関節や膝の安定性を高めることで、腸脛靭帯炎の症状改善が期待できます。腸脛靭帯炎の症状改善におすすめの筋力トレーニングは、以下のとおりです。
【下半身全体の筋力トレーニング(スクワット)】
- 立った状態で両足を肩幅程度に開く
- 背筋を伸ばしながら、ゆっくりと膝を曲げる
- 90度ほど膝を曲げたら、ゆっくりと伸ばす
- 2〜3の手順を20〜30回×2〜3セットを目安に行う
スクワットをする際は、関節に負担をかけないようにするために、膝がつま先よりも前に出ないように注意しましょう。
【中殿筋の筋力トレーニング】
- 横向きになって下側の膝を曲げ、上側の膝を伸ばす
- 上側の膝を伸ばしながら、ゆっくり真上に上げる
- 無理なく上げきったら、ゆっくり下ろす
- 2〜3の手順を10〜20回×2〜3セットを目安に行う
中殿筋(ちゅうでんきん)とは、骨盤の横についている筋肉で、股関節を広げる働きがあります。トレーニングの際は股関節を曲げず、膝と上半身を一直線にした状態で行いましょう。
再生医療
腸脛靭帯炎の治療において、「再生医療」を行っている医療機関もあります。再生医療とは、人が持つ自然治癒力を活用し、傷ついた組織の修復を促す治療法です。腸脛靭帯炎に対する再生医療として、おもに「PRP療法」があげられます。PRP療法とは、自身の血液から「血小板(けっしょうばん)」と呼ばれる成分を濃縮し、患部に注射する治療法です5)。血小板には、組織の修復を促進する成長因子が含まれているとされています。
再生医療は自身の組織を使用するため、副作用のリスクが低い点がメリットです。一方で、重度の症状には十分な効果がみられないケースもあるため、再生医療が適切かどうかを医師と相談する必要があります6)。
再生医療について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。
関連記事:再生医療 | ひざ関節の痛み解消ナビ
腸脛靱帯炎を早く治すためにやってはいけないこと
腸脛靭帯炎を早く治すために避けるべきことは、痛みを無視してそのまま運動を続けることです1)。炎症が起きている状態から、さらに負荷をかけ続けると症状が悪化する可能性があります。また、急激に運動強度を上げることも、症状を長引かせる原因となります。
重症化すると歩行時や安静時にも強い痛みが生じ、スポーツ復帰までの期間が大幅に伸びるおそれもあるでしょう。前述したように、軽症の段階で適切な休養と治療を行うことが、結果的に最も早い回復につながるのです。
腸脛靭帯炎の再発を防ぐための3つのポイント
腸脛靭帯炎の再発を防ぐためのポイントとして、以下の3つがあげられます。
- 運動前後のストレッチを心掛ける
- 下半身の筋力トレーニングを継続する
- 膝のサポーターやテーピングを活用する
ここでは、それぞれのポイントについて解説します。
1. 運動前後のストレッチを心掛ける
1つ目は、運動前後のストレッチを心掛ける点です。先ほど解説したように、ストレッチによって筋肉の柔軟性を高めておくと、腸脛靭帯にかかる負担の軽減につながります1)。
このときのポイントとして、運動後のストレッチも忘れないようにしましょう。運動後のクールダウンとしてストレッチすることで、筋肉の緊張をほぐして翌日に疲労を残しにくくなります。
2. 下半身の筋力トレーニングを継続する
2つ目は、治療後も下半身の筋力トレーニングを継続することです1)。筋力が低下すると運動時の膝や股関節の安定性が損なわれ、腸脛靭帯への負担が増加する原因となります。トレーニングは無理のない頻度で行い、痛みの状態に合わせて実施することが重要です。
また、トレーニング中に膝に違和感を覚えた場合は、すぐに中止して様子をみましょう。継続的な筋力トレーニングで膝まわりの安定性を高めれば、腸脛靭帯炎の再発予防が期待できます。
3. 膝のサポーターやテーピングを活用する
3つ目は、膝のサポーターやテーピングを活用することです。これらの道具は腸脛靭帯にかかる負担を軽減し、膝関節の安定性を高める効果が期待できます7)。膝のサポーターは装着が簡単で、日常的な運動時に気軽に使用できる点がメリットです。一方、テーピングはより細かな調整が可能で、個人の症状に合わせたサポートができるのが特徴です。
適切なタイミングでサポート用品を活用することで、腸脛靭帯炎の再発を予防しつつ、安心して運動を楽しめるようになります。
膝のサポーターの選び方は、以下の記事も参考にしてみてください。
関連記事:ひざサポーターの選び方は?着用の注意点・おすすめブランド3選
セルフチェックで腸脛靭帯炎だと思ったらすぐに医療機関への受診を
腸脛靭帯炎は、腸脛靭帯と大腿骨が擦れることで発症する疾患です。おもな症状は膝の外側の痛みや炎症で、そのまま放置するとさらに悪化するおそれがあります。腸脛靭帯炎の症状を改善するには、安静を心掛けて、痛みが落ち着いたタイミングでストレッチや筋力トレーニングを継続することが重要です。セルフチェックで腸脛靭帯炎の疑いがあると感じたら、なるべく早めに整形外科の医療機関を受診し、適切な治療を受けましょう。
【参考】
1)東京山手メディカルセンター|腸脛靭帯炎(ランナー膝)
2)日本臨床整形外科学会|鵞足炎
3)「ジャンパー膝に対する運動後のアイシングの効果」綾田 練、白木 仁, 体力科学(2007 )56, 125〜130
4)聖路加国際病院|膝複合靭帯損傷の診断と治療
5)北里大学|再生医療
6)東京女子医科大学|関節再生医療|人工関節
7)日本理学療法士協会|シリーズ 7 変形性膝関節症
記事監修者情報