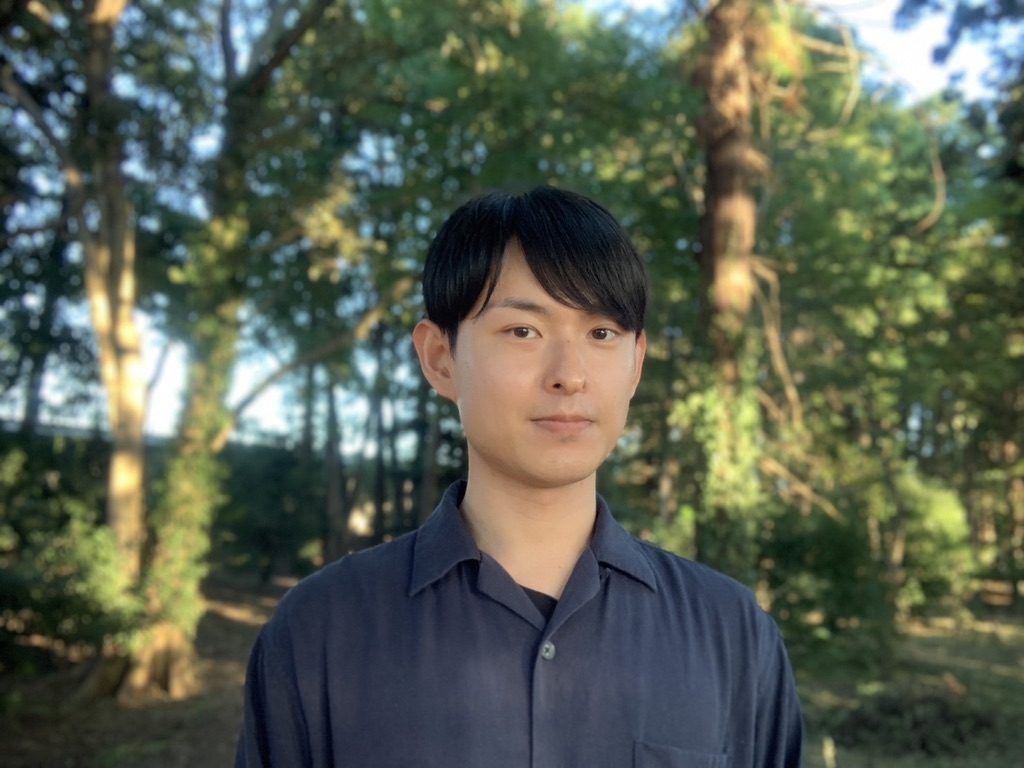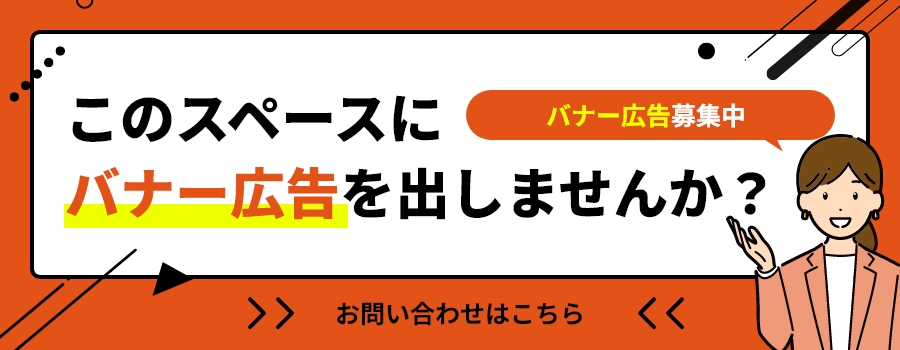記事監修者:内藤かいせい 先生

膝関節疾患の改善のために、往診やリハビリの利用を検討している方もいるのではないでしょうか。往診とリハビリはそれぞれサービス内容が異なるため、両者の特徴について把握しておくことが重要です。
この記事では往診の特徴や利用方法、リハビリサービスの種類をご紹介します。往診やリハビリについて知ることで、現在の症状に合った医療サービスを受けられるでしょう。
往診とは?膝関節の疾患でも利用できる?
往診とは、医師が利用者の自宅や施設に訪問して診療を行うサービスです。往診は突発的な病状の変化に対応するための臨時のサービスで、定期的に診療をするものではありません。患者さまやその家族からの要請を受けて、医師がその都度訪問して診察を行います1)。
往診を利用できる条件は、「診療の必要があると認められる場合」とされています2)。そのため、膝関節の疾患を抱えている方でも、症状が急変し診療が必要となった場合は利用可能です。膝関節の疾患を持つ方が往診を利用する際は、事前に症状を詳しく伝えておくことで、より適切な診察や処置を受けられます。
往診と訪問診療との違い
医師による在宅医療には、往診だけでなく訪問診療があります。どちらも医師が患者の自宅や施設を訪れて診療を行うサービスですが、その内容や目的は大きく異なります。
往診では急な体調変化や緊急時に医師が訪問するのに対して、訪問診療は定期的に行われる医療サービスです。週に1回や2週間に1回など、決められたスケジュールで医師が訪問するため、長期的にケアを受けられます1)。
訪問診療では定期的な診察に加えて、以下のようなことも行われます。
- 治療方針の見直し
- 薬の処方
- 医療相談
患者さまの状態や必要なケアの内容に合わせて、適切なサービスを選ぶことが大切です。
往診を利用するメリット

往診を利用することで、どのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、具体的なメリットをご紹介します。
通院せずに医師の診察を受けられる
往診サービスの最大のメリットは、通院せずに医師の診察を受けられる点です3)。膝関節の疾患を抱えている方は、身体に痛みを感じていたり、そもそも身体を動かしにくかったりという理由で、通院そのものが大きな負担となることがあります。公共交通機関やタクシーで通院する場合、費用面でも負担がかかるでしょう。
往診を利用すれば、自宅で診察を受けられます。これにより、移動にかかる負担や待ち時間などの問題を解消できるでしょう。膝関節の状態が悪化している方や、高齢で移動が難しい方にとって、このメリットは非常に大きいと言えます。
必要なときに利用できる
急変時や医師に相談したいときに利用できる往診なら、無駄なく医療サービスを受けられるでしょう。往診は訪問診療とは異なり、必要なときだけ利用するサービスなので、訪問診療と比べると医療費の負担を抑えやすい場合もあります。
往診のデメリット
往診のデメリットは、おもに以下のとおりです。
- 定期的な治療を受けられない
- 急変時の対応しかできないため、症状の早期発見が難しい
往診は医師がその都度訪問する仕組みなので、定期的な治療は受けられません。継続的なケアが必要な方であれば、往診よりも訪問診療のほうが適しているケースもあります。
往診には、利用者や家族が自覚できるような変化が生じたときに利用するという特性があります。そのため、隠れている症状や疾患の早期発見が難しく、対応が後手に回る懸念もあるでしょう3)。
このような往診のデメリットを補うためには、訪問診療をはじめとした在宅医療サービスの併用を検討する必要があります。
往診の費用はどのくらいかかる?
往診にかかる費用の目安は、数千円~1万円程度です(医療保険適用時)。ただし、診察内容や往診を受ける時間帯によっての費用は大きく変化することもある点に注意しましょう2)。
往診費用のほかにも、医師の交通費が別途必要となる場合もあります。具体的な費用は医療機関によって異なるため、往診を依頼する前に確認しておくことをおすすめします。
往診の利用方法
往診を利用する際は、おもに以下の3つの手順を踏む必要があります4)。
- かかりつけ医や医療機関に相談する
- 往診を依頼する
- 診療を受ける
往診を利用したい方は、まずはかかりつけ医に相談してみましょう。かかりつけ医の中には、これまで診療してきた患者のために往診に対応している医師もいます。かかりつけ医が対応できない場合も、地域の往診可能な医療機関を紹介してもらえることもあります。かかりつけ医がいない場合も、自分で往診対応の医療機関を探すことが可能です。
往診対応をしている医療機関は、こちらのページから検索できます。
往診で膝関節に対するリハビリを受けられる?
往診で膝関節に対するリハビリを直接受けることはできません。往診は医師による診察がおもな目的であり、リハビリ専門職によるサービスではないからです。しかし、医師の診断によって「リハビリが必要」と判断された場合、後ほどご紹介するリハビリサービスを受けられるようになります5)。
往診とリハビリを組み合わせることで、医療的な管理を受けながら、身体機能の改善を図れるでしょう。膝関節の問題で悩んでいる方は、まずは往診で医師の診断を受け、必要に応じてリハビリサービスの利用を検討してみましょう。
膝関節の疾患のリハビリを受けられるサービス
膝関節に関するリハビリを受けられるサービスは、おもに「訪問リハビリ」と「通所リハビリ(デイケア)」があります。ここでは、それぞれのサービスの特徴について解説します。
訪問リハビリ
訪問リハビリとは、理学療法士や作業療法士などの専門職が自宅に訪問し、リハビリを提供するサービスです6)。訪問リハビリの大きな特徴は、自宅環境に合わせたリハビリを受けられる点です。
例えば、自宅での階段の上り下りや床からの立ち上がりなど、実際の生活環境での動作に合わせたリハビリを受けられます。一方で、自宅でのリハビリとなるため、大規模な器具や治療機器などの使用ができない点に注意しましょう。
通所リハビリ
通所リハビリ(デイケア)とは、医療機関や介護施設に通い、そこでリハビリを受けるサービスのことです7)。通所リハビリの特徴は、訪問リハビリとは異なり、専門的な設備や機器を使ったリハビリを受けられる点です。
そのほかにも、以下のようなサービスも受けられるのも大きなメリットです。
- 食事
- 入浴
- 送迎
また、ほかの患者さまと交流しながらリハビリを受けられるのも、通所リハビリの良い点です。訪問リハビリと通所リハビリのどちらが適しているかは、患者さまの状態や生活環境によって異なります。ケアマネジャーやソーシャルワーカーと相談し、適切なサービスを選択しましょう。
膝関節の疾患のリハビリで行われる具体的な内容
膝関節の疾患に対しては、どのようなリハビリが行われるのでしょうか。ここでは、具体的なリハビリ内容をご紹介します。
運動療法
運動療法とは、身体を動かして関節の機能回復や筋力強化を図る治療法です。運動療法の種類は多岐にわたります。よく行われるものは以下のとおりです8)。
- 関節を動かす練習
- 筋力アップのトレーニング 筋トレ
- バランス練習
患者さまの状態に合わせて、これらの運動を継続して行い、膝まわりの筋力や関節の動きなど身体機能の改善痛みの緩和を目指します。
物理療法
物理療法とは、熱や電気などの物理的な刺激を利用して治療を行う方法です。物理療法には以下のように、さまざまな種類があります8)。
- 温熱療法
- 超音波療法
- 電気刺激療法
温熱療法では、患部を温めることで血行を促進し、筋肉の痛みや凝りの解消を図ります。超音波療法は、高周波の音波を使用して深部組織を温め、組織の修復を促す治療法です。また電気刺激療法は、筋肉に軽い電気刺激を与えることで、筋力強化や痛みの緩和に役立ちます。これらの物理療法の効果を高めるために、運動療法と組み合わせて行うこともあります。
動作指導
患者さまの身体状況に合わせて、安全に生活を送るための適切な動作方法を指導します。おもに、以下のような日常的な動作を確認・指導します。
- 歩行
- 階段の上り下り
- 立ち座り
- ベッドからの起き上がり
必要に応じて住環境の整備や福祉用具の使用も提案します。例えば、転倒しやすい場所に手すりを設置したり、移動時のふらつきを防ぐために杖を使用したりといった提案をします9)。
膝のリハビリについて、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。
関連記事:【理学療法士監修】膝の痛みに対するリハビリテーションとは?自宅でできるセルフケアもご紹介
必要に応じて往診とともに膝関節のリハビリを受けよう
必要なタイミングで医師が自宅を訪問し、診察や処置を受けられる往診には、通院の必要がないなどさまざまなメリットがあります。ただし、定期的な診察を受けるサービスではないため、場合によっては訪問診療のほうが適していることも。往診でリハビリを受けることはできませんが、訪問リハビリや通所リハビリを組み合わせることで、症状の緩和や改善が期待できるケースもあります。往診を検討している方は、まずはかかりつけ医やお近くの医療機関へ相談してみてください。
【参考】
1)日本訪問診療機構|訪問診療と往診の違い
2)地方創生|往診・訪問診療とは
3)品川区|在宅医療とは?
4)佐倉市|在宅療養が必要になったら
5)厚生労働省|訪問リハビリテーション(改定の方向性)
6)日本訪問リハビリテーション協会|訪問リハビリテーションとは
7)全国デイ・ケア協会|デイ・ケアとは
8)日本保健医療大学|理学療法とはどんな治療?対象になる人や受ける時期など詳しく解説
9)日本理学療法士協会|シリーズ 7 変形性膝関節症
記事監修者情報