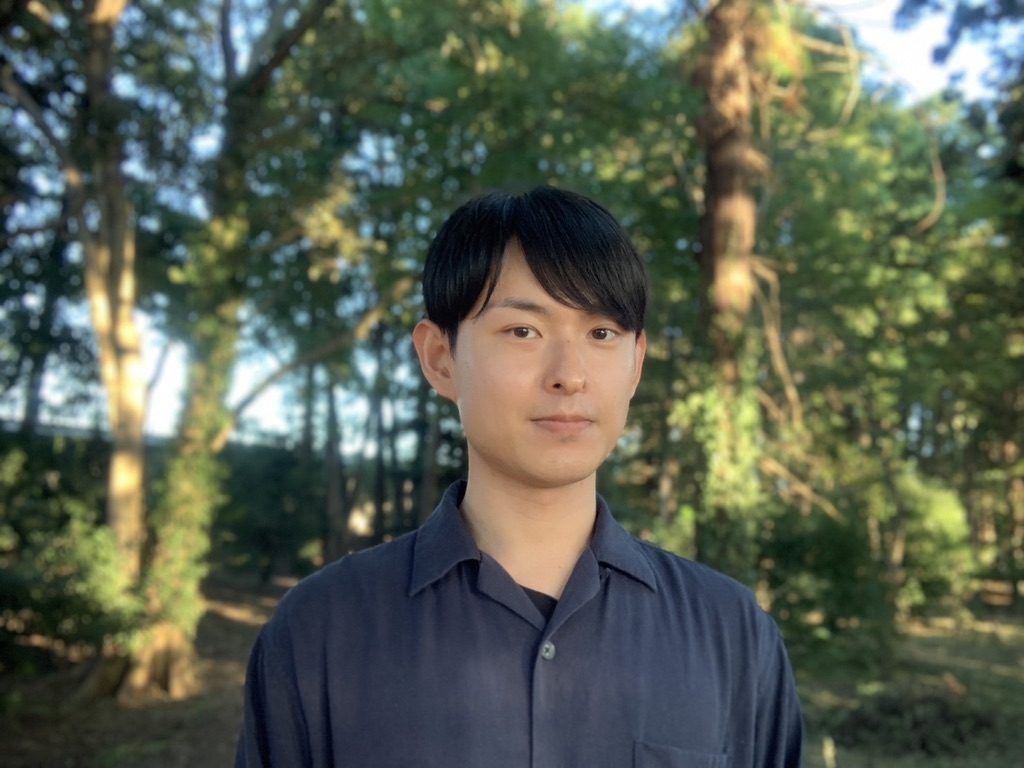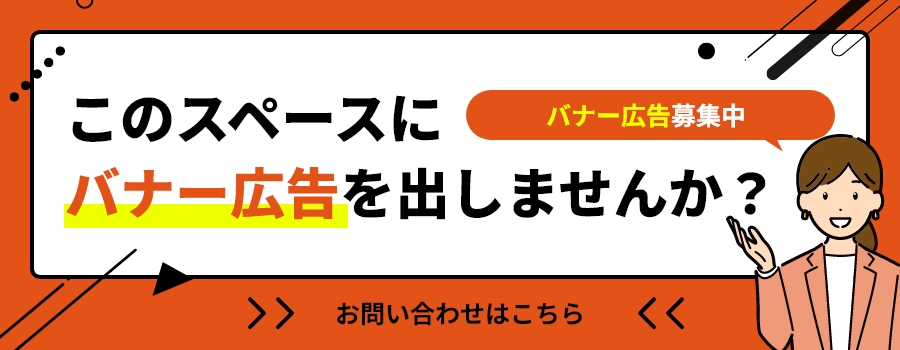記事監修者:内藤かいせい 先生
膝の痛みが強く、なかなか通院できない場合、在宅医療によるサポートを受けることも選択肢のひとつです。しかし、在宅医療とはどのようなサービスなのか、どのような支援を受けられるのかよく分からない方もいるのではないでしょうか。
この記事では、在宅医療の概要や利用するメリット・デメリット、具体的なサービスをご紹介します。在宅医療について知ることで、医療サービスを受ける際の新しい選択肢となるでしょう。
在宅医療とは?膝の痛みがある方も受けられる?
在宅医療とは、自宅をはじめとした生活の場に医療スタッフが訪問し、医療サービスを提供する仕組みのことです。在宅医療にはさまざまな種類があり、医師による訪問診療や看護師による訪問看護など、その方の症状に合ったサービスを受けられます1)。
在宅医療を利用できる対象者は以下のように幅広く、変形性膝関節症や関節リウマチなどで膝の痛みが強い方も含まれます2)。
- 高齢の方
- 寝たきりの方
- 病気を抱えている方
- 通院が難しい方
また自宅だけでなく、特別養護老人ホームやサービス付き高齢者住宅で過ごしている方も在宅医療の対象となります。
在宅医療の重要性
日本では高齢化が進んでおり、医療や介護を必要とする方が増加傾向にあります。その一方で、高齢化や病気によって身体機能が衰え、通院が難しい方も増えているのです。このような状況において、在宅医療は通院が難しい方の健康を支える重要な役割を担っています2)。
また、在宅医療は病院における病床不足の解消も期待できます。入院せず自宅で医療サービスを受けることで、より症状の重い患者さまのために病床を確保できるからです。このように、在宅医療は高齢者の生活の質を維持しつつ、医療体制を支えるうえで大きな役割を担っています。
なお、在宅医療を利用するためには、まずはかかりつけ医やお近くの医療機関で相談する必要があります。相談できる医療機関を探したい方は、こちらのページから検索してみてください。
在宅医療のメリット1)
在宅医療を利用すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、具体的なメリットをご紹介します。
住み慣れた環境で療養できる
在宅医療を選ぶメリットのひとつに、住み慣れた自宅で療養できることがあげられます。
通院や入院による環境の変化は、人によって大きなストレスとなります。入院生活は病院のルールに従う必要もあり、食事や入浴の時間など、生活リズムが制限されることもあるでしょう。自宅であれば、いつもの環境でリラックスした状態で治療を受けることが可能です。
通院の負担を軽減できる
在宅医療の利用は、通院による身体的・精神的負担を軽減できるメリットがあります。高齢者によっては通院が難しい、または移動に負担がかかる方もいるのではないでしょうか。とくに膝の痛みを抱える方にとっては、通院は大きな課題のひとつと言えます。
さらに、一人での通院が困難な場合、家族の送迎が必要になることもあるでしょう。在宅医療を利用すれば、移動や家族への負担の解消が期待できます。
経済的な負担を軽減できる
在宅医療は経済的な面でも大きなメリットがあります。入院の場合、治療費に加えて入院費や食事代など、さまざまな費用がかかります。
在宅医療であればこれらの出費を軽減し、通院にかかる交通費も削減可能です。病院が遠い、もしくは通う頻度が高いという場合には、大きな節約となるでしょう。経済的な負担を軽減したい方にとっても、在宅医療の利用はメリットが大きいと言えます。
在宅医療のデメリット・注意点1)
在宅医療はさまざまなメリットがある反面、デメリットや注意すべきポイントもあります。ここでは、具体的なデメリット・注意点について解説します。
治療内容に制限がある
在宅医療では、病院の設備に比べて利用できる医療機器が限られるため、治療内容も制限されます。病院では高度な医療機器を使った検査や治療を受けられますが、自宅ではそれらを実施することは困難です。膝の痛みに対する在宅医療を受ける場合、投薬や基本的なリハビリ、痛みの管理などが中心となるでしょう。
このような制限があるため、膝の痛みの症状によっては、定期的に病院に通院して検査や治療を受ける必要もあります。在宅医療を利用する際は自宅で治療を受けられる範囲と、病院での治療が必要になるケースを確認しておくことが大切です。
急変時に対応しにくい
病院では医師や看護師が常駐しているため、急な症状の悪化や緊急事態が発生してもすぐに対応できる環境が整っています。
一方、在宅医療では医療スタッフに連絡しても、到着までに時間がかかることも珍しくありません。急変時に家族が初期対応をしなければならないケースも多く、適切な判断や処置が難しい場合もあります。このようなリスクに対処するためには、在宅医療を受ける前に、急変時の連絡先や対応手順を家族や介護者と共有しておくことが重要です。
家族の介護負担がかかりやすい
在宅医療を選択すると、家族の介護負担が増加しやすいという課題もあります。在宅での生活となるため、医療スタッフが訪問している時間以外は家族が介護や見守りを担当することになります。家にいる以上、介護は24時間365日続くため、家族の精神的・身体的な疲労もたまりやすくなるでしょう。介護者が一人だけの場合、休息をとる時間が確保できずに介護疲れを起こしやすくなるという問題も生じます。
家族の介護負担を軽減するためには、ケアマネジャーに相談し、適切なサポート体制を構築することが大切です。在宅医療を選択する際はサービスを受ける本人だけでなく、家族の負担も十分に考慮したうえで、総合的に判断することをおすすめします。
膝の痛みに対する在宅医療の代表的なサービス3)4)
膝の痛みに対する在宅医療では、どのようなサービスがあるのでしょうか。ここでは、代表的なサービスについて解説します。
医師による訪問診療
訪問診療とは、医師が自宅に訪問して診療を行うサービスです。訪問診療では、利用者の体調や身体の状態などを診察し、必要に応じて薬の処方や治療方針の提案を行います。
例えば、膝の痛みが強くなっていないか、薬の効き目はどうかなどを確認します。急な体調変化や緊急時の対応方法についても相談でき、自宅でできるケアの指導も受けられる点も特徴です。
看護師による訪問看護
訪問看護とは、看護師が自宅を訪問し、医師と連携しながら以下のような支援を行うサービスです5)。
- 医療処置
- バイタルチェック
- 生活の援助
- 日常生活でのアドバイス
- 服薬管理
訪問看護を利用するメリットは、専門的な視点から日々の健康状態を見守ってもらえる点です。また医師との連携によって、必要に応じて迅速な対応が可能となります。
専門職による訪問リハビリ
訪問リハビリとは、医師の指示のもと理学療法士や作業療法士などの専門職が自宅を訪問し、リハビリを提供するサービスです。訪問リハビリでは、患者さまの身体機能を評価し、個々の生活環境や状況にあわせたリハビリプログラムを組み立てます。
具体的に行われるリハビリ内容は、以下のとおりです6)。
- 可動域を改善するためのストレッチ
- 筋力強化のためのエクササイズ
- 歩行訓練
- 動作指導
自宅の環境に合わせた運動や家具の配置の改善提案など、実生活に即したアドバイスを受けられるのも訪問リハビリの強みと言えるでしょう。膝の痛みがある方が訪問リハビリを定期的に受けることで、痛みの慢性化を防ぎ、身体機能の維持・改善が期待できます。
介護士による訪問介護
訪問介護とは、介護士が自宅での日常生活の援助やケアを行うサービスです。訪問介護では、おもに身体介護と生活援助のサービスがあげられます。身体介護では、以下のような生活の介助をしてくれます。
- 入浴
- 排泄
- 食事
- 衣類の着脱
- 移動の補助
生活援助では、以下のような家事を代行してもらえるのが特徴です。
- 掃除
- 洗濯
- 調理
- 買い物
膝の痛みがあると、生活での動作や家事などを行うのが難しくなる場合があります。訪問介護を利用することでこれらの負担が軽減されれば、膝の痛みの悪化予防にもなるでしょう。
膝の痛みに対する在宅医療の費用は?
膝の痛みに対する在宅医療の費用は、利用するサービスの種類や頻度、保険の自己負担割合によって大きく変化する点に注意しましょう。在宅医療の費用は大きく「医療費」と「介護費」の2つに分けられます。
医療費には訪問診療や訪問看護の費用が含まれ、自己負担割合は年齢や所得によって1〜3割と定められています。介護費は訪問介護や福祉用具の使用などにかかる費用で、65歳以上の方は介護保険が適用され、原則として1割が自己負担となります。ただし、特定の疾病により介護が必要な状態になった場合、40歳から64歳の方でも介護保険の利用が可能です7)。
これらの費用は個人によって大きく異なるため、正確な費用を知りたい場合は、ケアマネジャーやソーシャルワーカーに相談することをおすすめします。膝の痛みに対する在宅医療を検討する際は、医療面だけでなく経済面についても十分に理解し、無理のない範囲でサービスを利用することが大切です。
膝の痛みが強い場合は在宅医療の検討を
在宅医療には、自宅環境で療養できるほか、通院の負担を軽減できるなど、さまざまなメリットがあります。一方で、治療が制限されることや、急変時に対応しにくい点には注意が必要です。
在宅医療には訪問診療や訪問看護などのさまざまな種類があるため、その方に適したサービスを利用することが重要です。膝の痛みが強い方は、まずはかかりつけ医に相談してから在宅医療の利用を検討してみましょう。
【参考】
1)品川区|在宅医療とは?
2)全国在宅療養支援医協会|現代の在宅医療
3)環境再生保全機構|在宅医療・在宅療養の専門家・サービス・制度
4)市川市|在宅療養パンフレット
5)茨城県看護協会|訪問看護ステーションのサービス内容
6)日本理学療法士協会|理学療法士とは
7)在宅療養ガイド|在宅療養に関わるお金の話
記事監修者情報