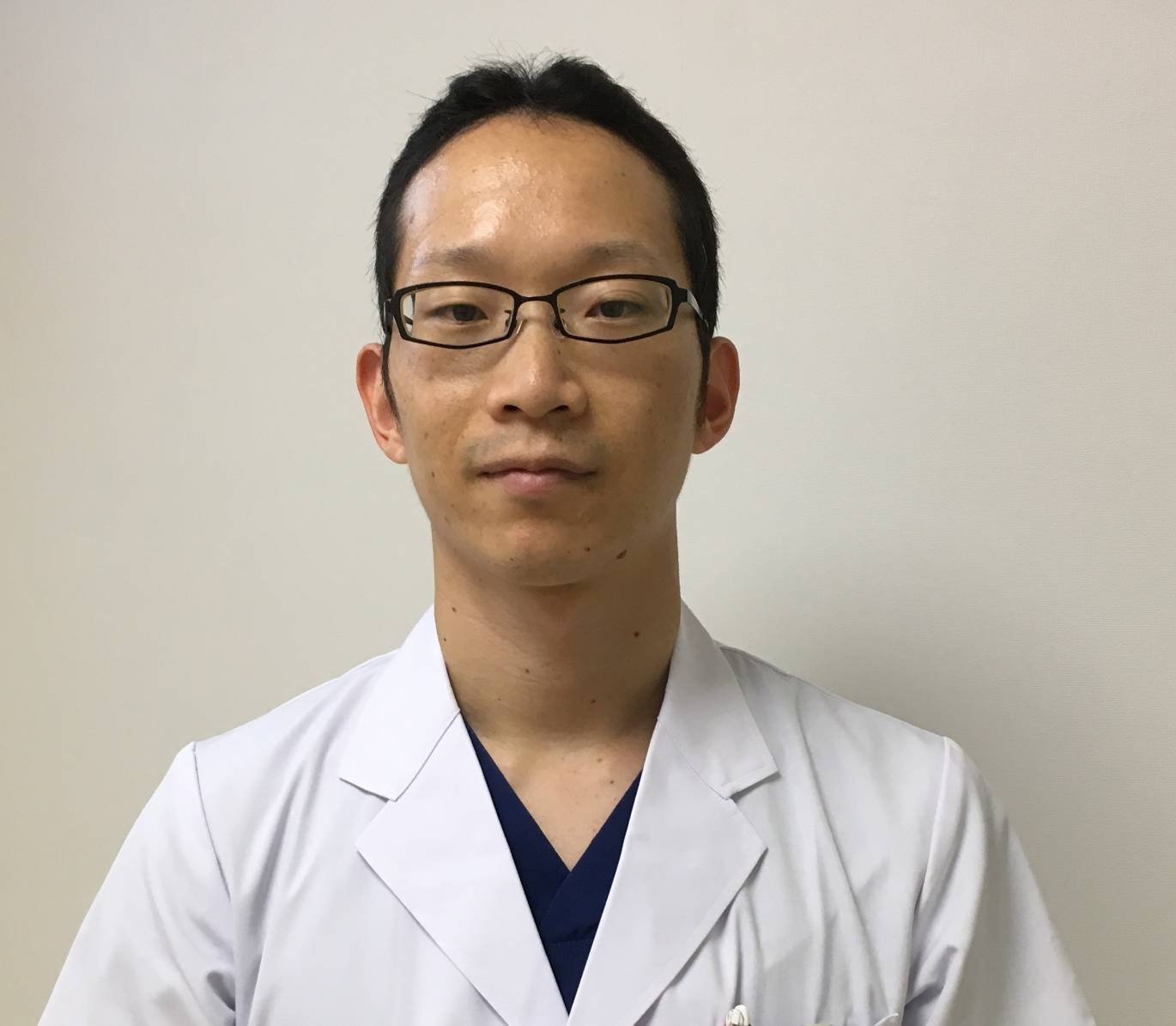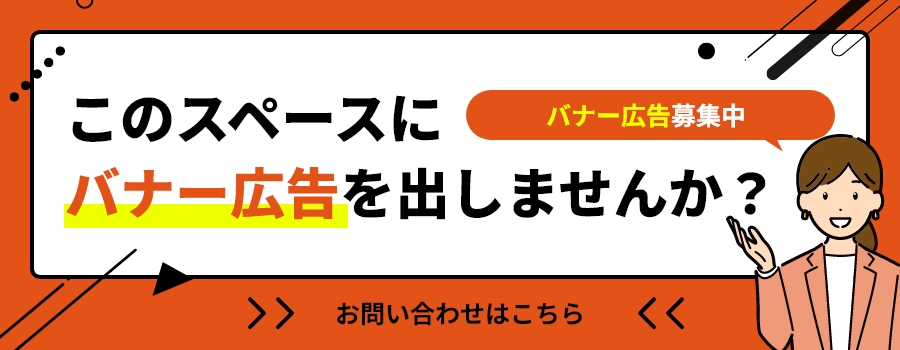記事監修者:松繁 治 先生
歩いているときや立っているときに、突然膝に力が入らなくなって膝が抜ける症状に悩む方もいるのではないでしょうか。膝が抜けやすくなる原因として、筋力の低下やケガによる影響などが考えられます。また、変形性膝関節症や靭帯損傷などの膝に関わる疾患を発症している可能性もあるでしょう。
この記事では、膝が抜けやすくなる具体的な原因やその対策をご紹介します。どのような原因なのかを明確にすることで、適切な対処ができるようになるでしょう。
膝が抜けやすくなる原因とは?
膝が抜けやすくなる原因として、どのようなものがあるのでしょうか。ここでは、おもな原因について解説します。
筋力の低下
膝が抜ける原因の1つとして、膝まわりの筋力低下があげられます。膝関節は太ももの前面にある「大腿四頭筋(だいたいしとうきん)」や裏側の「ハムストリングス」などの筋肉によって安定性を保っています。これらの筋肉が弱くなると、歩行時や立ち上がりの際に力が入りにくくなり、膝が抜けやすくなるのです1)。
とくに大腿四頭筋は膝を伸ばす働きがあるため、この筋肉が衰えている方は頻繁に膝崩れが生じやすくなります。膝まわりの筋力低下は以下のような、さまざまな要因で生じます。
- 加齢
- 運動不足
- 長期間の安静
膝まわりの組織の損傷
膝まわりの組織の損傷によって、膝が抜けることがあります。膝まわりには靭帯や軟骨などの組織がついており、これらは関節の安定性を高めたり、動きをスムーズにしたりする働きがあります。そのため、これらの組織が傷つくと膝の安定性が低下し、膝が抜けやすくなるのです2)。
組織の損傷は膝の疾患につながり、痛みや動きの制限などの症状も現れる場合もあります。ケガや激しい運動をしたあとに膝の抜けが出るようになった場合、組織の損傷を疑ってみましょう。
膝の痛み
膝の痛みがある場合も、膝が抜けやすくなります。膝に痛みを感じると、無意識に患部への負担を避けるために、膝に力を入れなくなることがあります。その結果、膝関節を支える筋肉がうまく働かず、歩行時や立ち上がる際に膝が抜けやすくなるのです3)。
痛みを避けるために不自然な歩き方になると、別の部位に悪影響が出る場合もあります。例えば、片方の膝が痛い場合、反対側に体重をかけて歩くこともあるでしょう。そうすると、反対側の膝にも痛みが生じることもあります4)。
膝が抜けやすいときに疑うべき疾患
膝が頻繁に抜ける場合、何かしらの疾患が疑われます。ここでは、考えられる疾患について解説します。
変形性膝関節症
膝関節の軟骨がすり減ることで起こる疾患です。軟骨がすり減ると骨同士が直接こすれることにより痛みが出たり、関節の安定性が低下し、膝がカクッと抜けやすくなります。そのほかにも、膝の腫れや動かしにくさなどの症状も特徴的です。症状が進行すると、安静時でも膝に痛みを感じたり、膝関節が変形したりして歩行が困難になる場合もあります。
変形性膝関節症の代表的な原因は、加齢による半月板の変性や軟骨組織の老化があげられます。そのほかにも、肥満による軟骨の負担増加や、ケガの後遺症によって発症することもあるでしょう5)。
変形性膝関節症については、以下の記事も参考にしてみてください。
前十字靭帯損傷
前十字(ぜんじゅうじ)靭帯損傷とは、膝関節の中にある「前十字靭帯」と言う靭帯が損傷する疾患です。前十字靭帯は、膝関節を構成する太ももの骨(大腿骨)とすねの骨(脛骨)をつなぐ靭帯で、以下の役割があります6)。
- 膝関節の前後の安定性を高めている
- 膝が過度にねじれないようにしている
この靭帯が損傷すると膝が不安定になり、歩行中や動作中に膝が抜けやすくなるのです。前十字靭帯損傷は、スポーツ中でよくあるジャンプ後の着地や急な方向転換などがきっかけで発症します7)。膝が抜けやすくなる以外にも、痛みや腫れなどの症状をともなうこともあります。
膝関節には前十字靭帯だけでなく、さまざまな靭帯がついています。膝靱帯については、以下の記事もぜひご覧ください。
関連記事:【医師監修】膝靱帯の痛みがあるときの対処法は?代表的な疾患や治療法を解説
半月板損傷
半月板(はんげつばん)損傷とは、「半月板」と言う膝関節内にある組織が損傷する疾患です。半月板にはクッションのような役割があり、関節の安定性を保ち、動きをサポートする働きをしています8)。半月板損傷を発症すると関節に加わる負荷をうまく分散できず、以下のような症状が現れます9)。
- 膝の痛み
- 膝のひっかかり感
- 膝崩れ
半月板損傷はスポーツでの急な動きや方向転換などで発症しやすく、前十字靭帯損傷が合併することもあります。また、加齢によって半月板が衰えて発症するケースも少なくありません。
半月板損傷については、以下の記事でも詳しく解説しています。
関連記事:【医師監修】半月板損傷とは?半月板の役割や治療法、予防法もあわせて紹介
繰り返し膝が抜けるとどうなる?
繰り返し膝が抜けると、さまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。膝崩れと言う現象自体も、膝に負担がかかる原因の1つです。繰り返し膝が抜けると関節への負担が蓄積され、やがて軟骨や半月板が損傷し、変形性膝関節症をはじめとした疾患を引き起こす恐れがあります10)。
膝が抜けるような症状を感じたら、その原因を特定して適切な治療を早めに受けることが大切です。
膝が抜けるときの診断方法
膝が抜ける症状の原因を特定するには、いくつかの診断があります。まず、痛みや違和感などの症状の有無を確認しつつ、関節のゆるみや不安定さなどをチェックします11)。
さらに診断をするうえで重要なのが、画像検査です。一般的にはレントゲン検査が行われ、骨の状態や関節の隙間などを確認します。靭帯や半月板などの組織の損傷を確かめる場合は、MRI検査を行うこともあるでしょう8)。膝が抜ける症状にはさまざまな原因が考えられるため、複数の検査結果をもとに総合的に判断する必要があります。
頻繁に膝が抜ける場合の対策
頻繁に膝が抜ける場合、どのような対策が必要なのでしょうか。ここでは、具体的な対策をご紹介します。
膝まわりの筋力の強化
膝まわりの筋肉の衰えが原因で膝が抜ける場合、筋力をつけることが大切です。膝まわりの筋力をつけることで、膝関節の安定性が高まり、膝崩れの改善が期待できます。気軽に膝まわりの筋肉を鍛えられるトレーニングをご紹介します12)。
【スクワット】
- 立った状態でテーブルや壁に手を添える
- 背筋を伸ばして足を肩幅程度に開く
- ゆっくりと膝を曲げる(膝がつま先よりも前に出ないようにする)
- 膝を90度ほど曲げたら、ゆっくりと伸ばす
- 3〜4の手順を10〜15回×2〜3セットを目安に行う
スクワットは大腿四頭筋や太もも後面の「ハムストリングス」など、下半身全体の筋肉を鍛えられます。
【お尻上げ】
- あお向けになり、両膝を立てる
- 両膝を閉じて、お尻を上げる
- 太ももと上半身が一直線になるまで上げたら、ゆっくりと下ろす
- 2〜3の手順を10〜15回×2〜3セットを目安に行う
お尻上げは、お尻の筋肉の「大殿筋(だいてんきん)」やハムストリングスを鍛えられるトレーニングです。
整形外科のある医療機関を受診する
膝が抜ける以外にも、痛みや動かしにくさがある場合は、何かしらの疾患を発症している可能性があります。その場合は整形外科の医療機関を受診し、医師に診断してもらいましょう。医療機関への受診を先延ばしにすると、症状が悪化して日常生活に支障をきたしやすくなります。膝に違和感を覚えたら早めに医師に相談し、適切な診断と治療を受けることで、症状の改善につながります。
お住まいの近くで整形外科のある医療機関を探したい方は、こちらで検索してみてください。
治療を受ける
医療機関を受診し、何かしらの疾患を発症した場合、症状に合わせた治療を受けましょう。具体的な治療法は、おもに以下の3つがあげられます。
- 保存療法
- 手術療法
- 再生医療
ここでは、それぞれの治療内容について詳しくみていきましょう。
保存療法
保存療法とは、手術以外の方法で改善を目指す治療法で、症状が軽度から中等度の場合に効果的です。保存療法では、おもに以下のような治療が行われます13)。
- 薬物療法
- 装具療法
- リハビリ
膝の痛みや炎症がある場合、症状をやわらげるために鎮痛剤が処方されます。装具療法で使用するものとして代表的なのが、膝サポーターです。膝サポーターの着用によって膝関節の安定感を高めて、膝崩れの防止を図ります。また、リハビリでは先ほど解説したように、筋力トレーニングによって膝まわりの筋肉を鍛えて、関節の安定性を高めます。
手術療法
保存療法で膝崩れが改善しない場合や、症状が重い場合は手術が検討されます。手術の内容は、疾患によって大きく異なります。
例えば、変形性膝関節症の方で症状が進行している場合、「人工関節置換術」が行われることがあるでしょう。人工関節置換術とは、膝関節を人工物に入れ換える手術で、これにより関節のすり減りによる痛みの改善が期待できます13)。前十字靭帯損傷であれば、ほかの部位の組織を使い、切れた靭帯の代わりを作る「再建術」が行われます6)。
再生医療
膝の疾患に対する新たな選択肢として、再生医療が注目されています。再生医療とは、人に備わる自然治癒力を活かし、損傷した組織の修復や機能回復を促す治療法です。
再生医療の代表的な治療法に、「PRP(多血小板血漿)療法」があります。これは自身の血液内の「血小板(けっしょうばん)」と言う、組織の修復を促す働きのある成分を濃縮し、それを患部に注射する治療法です14)。PRP療法では、膝の痛みの軽減や関節の動きやすさの改善が期待できます。ただし、再生医療は重度の症状がある方にはあまり効果が得られない可能性がある点に注意が必要です15)。
再生医療については、以下の記事も参考にしてみてください。
関連記事:再生医療 | ひざ関節の痛み解消ナビ
膝がよく抜ける原因は疾患の可能性もある
膝が抜けるのを改善するためには、その原因について把握しておくことが重要です。何かしらの疾患を発症している可能性もあるため、膝崩れが続く場合は整形外科のある医療機関への受診をおすすめします。
早期から治療を進めることで膝の抜けが改善され、いつもの日常生活を送れるようになります。ぜひ今回の記事を参考にして、膝が抜ける際の対策についておさえておきましょう。
【医師からのコメント】
膝が抜けるといった症状は、変形性膝関節症や靭帯断裂など膝関節自体が原因のものもあれば、膝以外が原因で起こることもあります。膝以外が原因で比較的多いものとしては、腰が関係する腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症などです。その症状としては、腰から臀部、下肢全体や一部分にかけての痛みが出現し、いわゆる「坐骨神経痛」として知られています。
これらの病気は痛みだけでなく、ひどくなると下肢の筋力低下を合併することもあります。筋力低下が軽度であれば、痛みが強いときに急に膝が抜けるような感じを自覚することがありますし、筋力低下がひどくなれば足に力が入らずに歩けないといった症状を訴えられる方もいます。
膝の痛みがあり、整体や接骨院でマッサージをされる方などもいらっしゃいますが、それでも良くならない場合は、整形外科を受診して精密検査などを受けるようにしましょう。
【参考】
1)「階段後段時に右下肢の支持性低下を認めた右変形性膝関節症患者の一症例 ー右膝回旋不安定性に着目してー」清水 啓介、井上 隆文ら 関西理学 12:61-68, 2021
2)村山医療センター|膝関節疾患の治療 前十字靭帯損傷
3)北里大学|変形性膝関節症
4)医科歯科総合病院|ひざの痛みと全身のバランス
5)日本整形外科学会|変形性膝関節症
6)順天堂医院|膝前十字靭帯損傷
7)日本スポーツ整形外科学会|6.膝前十字靱帯損傷
8)日本スポーツ整形外科学会|33.半月板損傷
9)順天堂医院|膝半月板損傷
10)関東労災病院|膝前十字靭帯損傷について
11)東邦大学|膝鏡視下手術
12)日本理学療法士協会|シリーズ 7 変形性膝関節症
13)慶應義塾大学病院|変形性膝関節症
14)北里大学|再生医療
15)東京女子医科大学|関節再生医療|人工関節
記事監修者情報