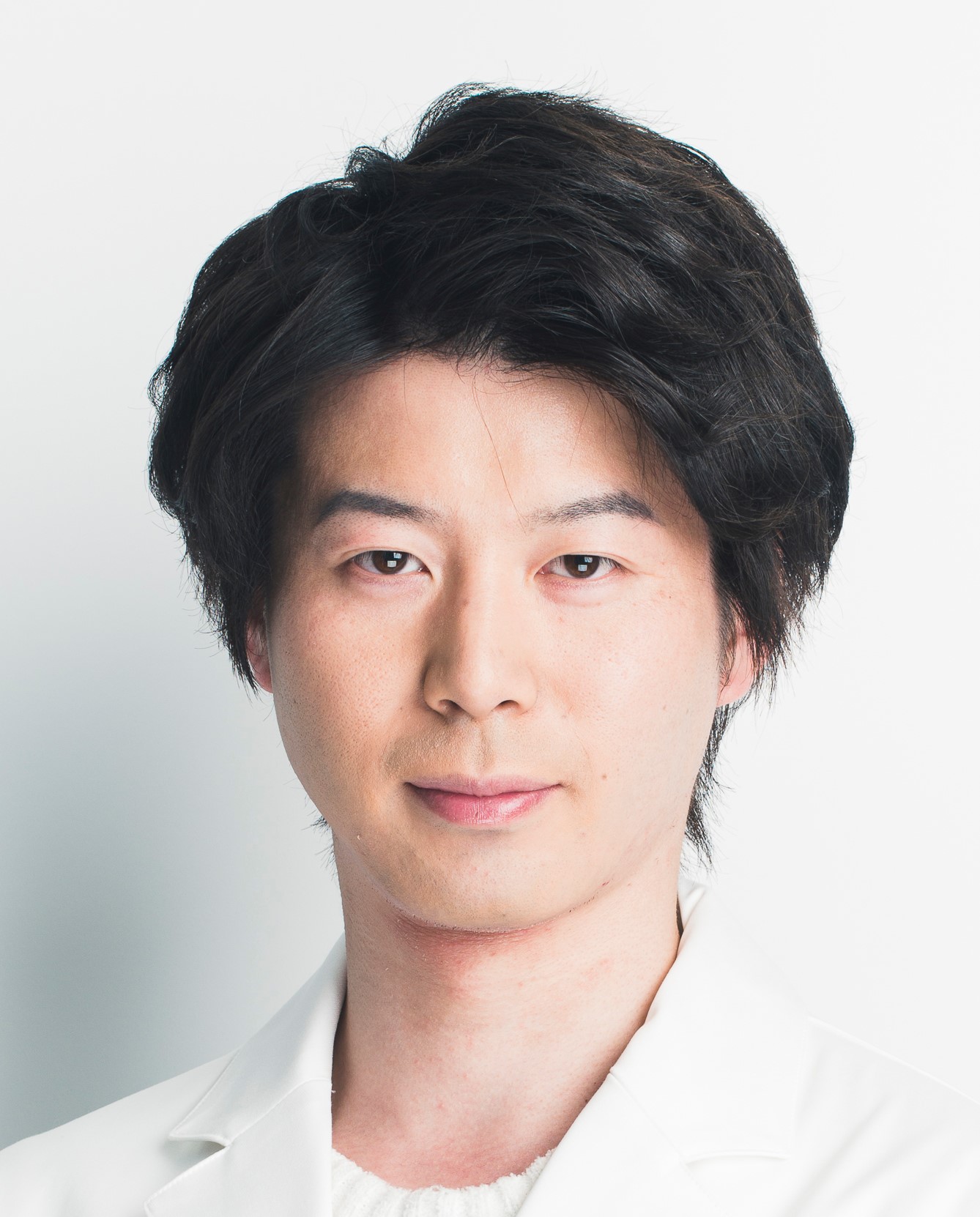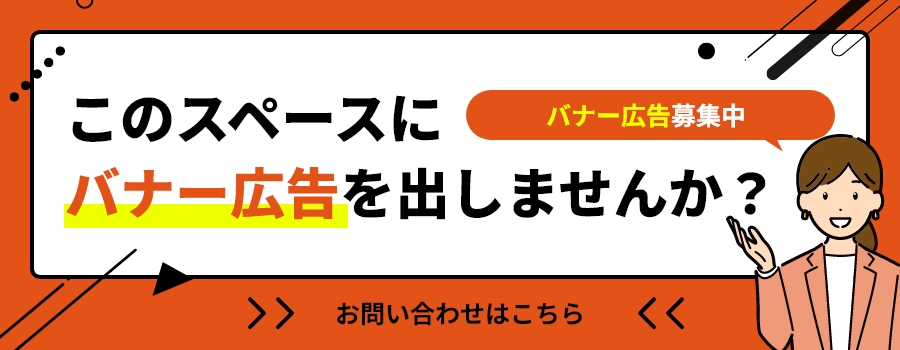記事監修者:眞鍋 憲正 先生
骨粗しょう症とは、骨がもろくなり骨折しやすくなる病気です。初期は自覚症状があまりなく、骨折して初めて骨がスカスカな状態であることが判明することもあります。骨粗しょう症はそれ自体が命に関わる病気ではありませんが、高齢者の場合、骨粗しょう症で骨折したことが原因となって寝たきりや介護になり、結果として死亡リスクを高めることにつながります。
ここでは、骨粗しょう症のメカニズムや症状、検査、治療法、予防法を総合的に紹介します。心当たりのある方はご自身の症状と照らし合わせながら参考にしてみてください。
骨粗しょう症とは?
骨粗しょう症とは、骨がもろくなり骨折しやすくなる病気です。骨の強さは、70%が「骨量」(骨に含まれるカルシウムやマグネシウムの量)で残りの30%は「骨の質」で決まると言われていますが、骨粗しょう症は骨量や骨の質が低下して骨折のリスクが高まる病気です。
骨粗しょう症のメカニズム
実は、人間の骨は新陳代謝をしています。「骨吸収」といって古くなった骨が毎日少しずつ溶けていく一方で、骨芽細胞が新たに骨を作る「骨形成」も同時に起きており、これを「骨リモデリング」と呼びます。通常は骨吸収と骨形成が同じように起きて強度が保たれますが、このバランスが崩れて骨吸収のスピードが骨形成を上回ると、骨の強度が徐々に低下していき骨粗しょう症に繋がります。
骨粗しょう症の原因1)
骨粗しょう症の原因はさまざまです。詳しく紹介していきましょう。
原因①加齢
骨粗しょう症の原因で最も多いのは「加齢」です。一般的に骨の強度は男女ともに20代がピークで、その後は徐々に低下します。歳を重ねると骨リモデリングのスピードが落ちていくことは、避けられない事実です。若いうちに骨の強度をつけて、できるだけピークを高い状態にしておくことや、低下のスピードを緩やかにすることが重要です。
原因②女性ホルモンの低下
女性ホルモンのエストロゲンは骨吸収を緩やかにする効果があるのですが、閉経を迎えてエストロゲンが減少すると骨吸収のスピードが一気に速くなります。
原因③運動不足や無理なダイエット
骨は負荷をかけるほど骨を作る細胞が活性化するため、外出の機会が少なく運動不足の方は骨粗しょう症になりやすいと言えるでしょう。ダイエットによる栄養不足や、過度な飲酒や喫煙の習慣も骨に悪影響を及ぼします。
原因④特定の病気や薬など
特定の病気や服用している薬が原因となって発症する場合もあります。下記の病気の患者さまは、とくに骨粗しょう症に注意が必要です。
・糖尿病
・慢性腎臓病
・動脈硬化
・関節リウマチ
・甲状腺機能亢進症、副甲状腺機能亢進症
・肝臓病
・慢性閉塞性肺疾患 など
骨粗しょう症にかかりやすい人 2)
骨粗しょう症の患者さまの約80%が女性です。とくに、閉経後の高齢女性は骨粗しょう症にかかりやすく、実際に60代女性の約5人に1人、70代女性の約3人の1人は骨粗しょう症と言われています。ほかにも、下記のような特徴がある人は骨粗しょう症にかかりやすい要因があると言えるでしょう。
・閉経後の女性
・60歳以上の男性
・細身で体重が軽い
・過去に無理なダイエットをした
・骨折したことがある
・両親のどちらかが太ももの付け根を骨折したことがある
・寝たきりなど運動量が不足している
・カルシウムを意識した食事をしていない
・日常的に多量の飲酒をしている
・タバコを吸っている
・ステロイド薬を長期間使っている
・骨粗しょう症の原因となる病気を持っている など
骨粗しょう症の症状
骨粗しょう症は、初期には自覚症状がないことが多い病気です。しかし、まれに下記のような症状が出ることがあります。
・身長が縮んでくる
・背中や腰が曲がってきた
・背中や腰に痛みがある
・背中が曲がってしまい胸焼けがする
・背中が曲がってしまい息切れする
骨粗しょう症の恐ろしいところ
骨粗しょう症は、それ自体が命を脅かす病気ではありませんが、気付かぬうちに進行します。ちょっとした衝撃で骨折してしまうと、次々と骨折が起こる可能性があります。この骨折の連鎖を「ドミノ骨折」と呼びます。また、高齢者が背骨や大腿骨の骨折をしてしまうと寝たきり状態になるケースもあるほか、手術や感染症、心肺機能が低下するなどのリスクが発生し、最悪死に至ることがあります。また、死亡することはなくても、骨折によって自由に動けなくなると生活の質が低下しますし、肺炎や深部静脈血栓症などの合併症を引き起こしやすくなります。
ある調査によると、骨粗しょう症で大腿骨を骨折した人の5年生存率は49%1)という驚きの数字が出ています。2014〜2015年に診断されたがんの5年生存率は66.2%2)ですので、骨粗しょう症はある意味、がん以上に死亡率が高い怖い病気と言えるでしょう。
骨粗しょう症の検査4)
もしかして骨粗しょう症かも、と思ったら病院で検査を受けてみましょう。骨粗しょう症の検査は大きく分けて「骨密度検査」「X線検査」「骨代謝マーカー」の3つです。
骨密度測定
骨にミネラル成分(カルシウムやリンなど)がどれほど含まれているかを測定し、骨粗しょう症のリスクを判定します。骨密度測定には3つの測定法があります。
二重エネルギーX線吸収法(DXA)
2種類のX線を骨に当てることで骨密度を測る測定法です。骨粗しょう症の検査では、背骨や太ももの付け根、前腕などの骨密度を測定します。通常のレントゲン写真撮影と比べて被ばく量が少なく精度が高いですが、この測定法ができる病院は限られています。
MD法
手の骨密度をX線で測定します。一般的なX線撮影装置で簡便に測定できますが、薬による骨密度の上昇効果まで判定しにくいというデメリットがあります。
定量的超音波測定法(QUS)
X線ではなく、超音波が踵の骨の中を伝わる速度を測ることで骨密度を評価する測定法です。診断には使われませんが、検診などでも持ちいられる簡単な方法として普及しています。被ばくしないのもメリットのひとつです。
レントゲン撮影
脊椎を構成する骨である椎体(ついたい)に骨折や変形がないかレントゲン写真を撮影して確認します。病院によっては、X線検査より詳しく分かるMRI検査を行うこともあります。
骨代謝マーカー
血液や尿検査によって測定する方法で、骨の新陳代謝の活発さを知ることができます。骨代謝マーカーの高い人は骨折の危険性が高いうえ、骨密度の低下が著しく、骨粗しょう症のなりやすさとも関連すると言われています。
骨粗しょう症の診断
病気や服薬を原因としない「原発性骨粗しょう症」の場合、X線で骨のもろさによる骨折があるかないかに加え、先に紹介した骨密度検査の結果を加味して診断されます。
骨粗しょう症の治療5)
骨粗しょう症の治療法には、食事療法、運動療法、薬物療法があります。どれもコツコツと続けているうちに、骨の新陳代謝が改善し骨密度がアップしていきます。なかなか効果が出ないからと自己判断で中断しないことが大切です。それでは3つの治療法をそれぞれ詳しく紹介していきます。
薬物療法
治療の中心になるのは薬物治療です。飲み薬や注射などのタイプがあり、医師は患者さんの症状や年齢、骨粗しょう症の原因、骨折のリスク、既往症、ライフスタイルなどを考えて処方薬を決めていきます。薬剤によって異なりますが副作用もありますので、事前に医師に相談しましょう。
なお、頻度は少ないですが、長期間薬物療法を続けていると、歯科治療で抜歯を行った際に顎の骨が腐る「顎骨壊死」という病気が発生する可能性があります。これは、薬剤の影響で抜歯後の歯茎が治りにくいため、そこに細菌が入り込み、炎症が顎まで波及することで引き起こされる病気です。骨粗しょう症の治療を始める前に、歯科治療を終わらせておくといいでしょう。
骨粗しょう症の治療薬はその目的から大きく5つに分けられますので、それぞれ代表的な薬を紹介します。
骨吸収を抑える薬
・ビスホスホネート
・選択的エストロゲン受容体作働薬(SERM)
・抗RANKL抗体
骨形成を促進する薬
・副甲状腺ホルモン薬
骨吸収を抑え、骨形成を促進する薬
・抗スクレロスチン抗体
骨に必要な材料を補充または骨代謝をサポートする薬
・カルシウム
・活性型ビタミンD3
・ビタミンK2
その他
・カルシトニン
食事療法
骨粗しょう症の食事指導では、カルシウム、ビタミンD、ビタミンKを摂取しながら、エネルギーをはじめとした栄養素をバランスよく摂るのが基本です。食が細い方は、医師と相談したうえで、サプリメントなどで栄養を補うこともあります。
骨粗しょう症の治療時におすすめな食品
・カルシウムを多く含む、牛乳・乳製品・大豆製品・緑黄色野菜・小魚など
・ビタミンDを多く含む、魚やきのこ、卵など
・ビタミンKを多く含む、納豆、緑色野菜など
骨粗しょう症食品の治療時には控えめにした方がいい食品
・スナック菓子、インスタント食品
・アルコール
・カフェインを多く含むコーヒー など
運動療法
骨は負荷がかかるほど骨を作る細胞が活性化するという特徴があるため、ジャンプやジョギング、エアロビクスなど重力がかかる運動の方がより効果的です。ただ、骨粗しょう症の治療をしている方にとって、これらの運動は転倒や骨折のリスクも高まるため、散歩や階段の上り下りなど日常生活のなかで安全にできる運動を取り入れることが大事です。
骨粗しょう症の予防法
骨粗しょう症や骨折を防ぐためにはどのようなことに気を付けるといいのでしょうか。日常生活の中での注意点を紹介します。
骨折予防
先に紹介した骨を強くする食事法や運動法を参考に、カルシウムやビタミンDを意識したバランスのいい食生活と適度な運動習慣を心がけましょう。また、紫外線を浴びることでビタミンDが体内で作られます。冬は30〜60分ほどの散歩、夏は直射日光を避けられる木陰で30分ほど過ごすだけで十分ですので、日光を浴びることも意識していきましょう。
転倒予防
高齢者の転倒事故の多くが家の中で起こっています。骨粗しょう症の予防だけではなく、住環境を見直して、骨折につながる原因をできるだけ排除しておきましょう。
こんなところをチェック!
・床にものを置きっ放しにしない
・生活動線にコードなどが出ないようにする
・玄関など段差のあるところにスロープや台を置く
・浴室や階段、トイレなどに手すりをつける
・寝室の枕元や廊下の足元に照明を置く
・滑りやすい靴下、スリッパを履かない
・外出する際は滑りにくい靴で、雨の日や夜は特に注意する
骨粗しょう症の検診
骨粗しょう症は発症しても自覚症状のないことが多く、実際に骨折が起きて初めて気付くことが多い病気です。予防には自分の骨の強さ(骨強度)や状態を把握することが重要なため、50歳代になったら定期的に検査を受けましょう。骨粗しょう症の相談は整形外科を受診するのが一般的ですが、内科や婦人科でも診てもらえることがあります。
また、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の女性を対象に、国が行う「骨粗しょう症検診」も行われています。お住まいの自治体のホームページ等を確認し、積極的に活用するのがおすすめです。
自覚症状がなくても50歳を迎えたら骨粗しょう症の検査をしよう
QOLに大きく影響を与える骨粗しょう症について紹介してきました。骨粗しょう症がもたらす最悪のストーリーを防ぐためには、早めのケアが大切です。自覚症状が少ない病気ですので、50歳を迎えたら定期的に病院で検査を行うように心掛けましょう。
【医師からのコメント】
骨粗しょう症の恐ろしい点は、背骨(椎体)や大腿骨近位部の骨折につながることです。これらの骨折は、疼痛と運動制限を招き、ADL低下から寝たきり、介護依存、さらには健康寿命の大幅な短縮につながります。これを防ぐには、骨形成を促す負荷歩行やレジスタンストレーニング、バランス訓練などの運動療法が欠かせません。定期的な下肢筋力強化と体幹安定運動により転倒リスクを抑制し、骨強度を維持することで、寝たきり回避と健康寿命延長に大きく寄与します。
また、万が一骨折してしまったあとも、長期臥床は筋萎縮や肺炎リスクを高め、回復後も歩行機能が低下しやすくなるためやはり運動療法は重要です。環境整備や栄養管理の徹底も予防に欠かせません。特に閉経後女性や高齢者はリスクが高いため、定期的な骨密度検査と運動習慣の見直しをしましょう。
【参考】
記事監修者情報