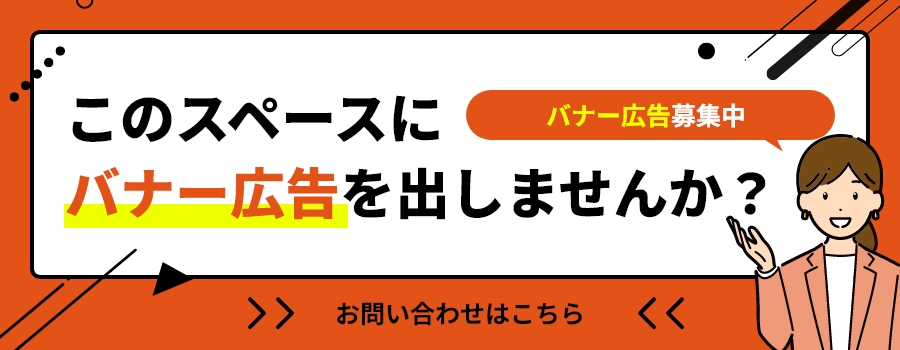記事監修者:松澤 宗範 先生
スポーツをするときにケガをしてしまい、その治療法で悩んでいる方もいるのではないでしょうか。スポーツ外傷に対する治療法のひとつに、再生医療があげられます。実際に、スポーツ選手が再生医療を受けてケガを治したという事例も少なくありません。
この記事では、スポーツ外傷の種類や再生医療の詳細をご紹介します。どのような治療なのかを知ることで、ケガを治す際の選択肢が広がるでしょう。
スポーツ外傷の特徴
スポーツ外傷とは、スポーツ中に発生するケガのことです。このトラブルは、大きく「外傷」と「障害」の2つに分類されます1)。外傷は転倒や衝突などで生じる外的要因のケガで、以下のような症状が当てはまります。
- 打撲
- 骨折
- 捻挫
- 肉離れ
一方で、障害は過度な負荷が繰り返し起こることで発症します。当てはまる症状は以下のとおりです。
- 疲労骨折
- 関節炎
- 腰椎椎間板ヘルニア
実際のスポーツ現場では、この2つの区別がはっきりしないケースもあります。いずれにせよ、スポーツ外傷が起こった場合は、早期対応・早期治療が重要です。
代表的なスポーツ外傷の種類
スポーツ外傷には、さまざまな種類があります。ここでは、具体的なスポーツ外傷の種類をご紹介します。
筋肉の損傷
スポーツ外傷として起こりやすいのが、筋肉の損傷です。筋肉の損傷は軽傷から重症まで幅広く、その状態に適した治療が欠かせません。代表的な筋肉の損傷として、筋肉痛や肉離れなどがあります。筋肉痛は、筋線維(筋肉を構成する線維)の細かな損傷によって起こる痛みです。肉離れは筋線維が部分的に断裂した状態で、筋肉痛よりも強い痛みを引き起こす傾向にあります2)。
いずれも、スポーツ中の急な動きや筋肉への過度な負荷によって発生します。筋肉の損傷の多くは自然治癒が見込めますが、痛みが強い場合や症状が長引く場合は医師の診察を受けることが重要です。
靭帯や腱の損傷
関節に強い力がかかると、その周囲の靭帯や腱(筋肉の末端の部分)が損傷することがあります。靭帯や腱は関節の安定性を高める働きがあるため、これらの組織が損傷すると日々の動作に支障をきたしやすくなります。
代表的な靭帯・腱の損傷例は、以下のとおりです3,4)。
- 側副(そくふく)靱帯損傷:膝関節の左右についている靭帯の損傷
- 前十字(ぜんじゅうじ)靭帯損傷:膝関節の中についている靭帯の損傷
- 腱板(けんばん)断裂:肩関節についている腱の集まりの損傷
これらの損傷や断裂は、関節の過度の使用や急な衝撃などによって発症します。損傷の程度によっては、手術が必要となることもあります。
膝の靭帯損傷についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。
関連記事:【医師監修】膝靱帯の痛みがあるときの対処法は?代表的な疾患や治療法を解説
関節に関係する組織の損傷
関節に負荷がかかると、その周辺にある組織も損傷することがあります。代表例に、膝関節内にある半月板(はんげつばん)の損傷があります。半月板とは、膝関節内についているC字型の軟骨で、クッションのように体重を分散させる役割があるのが特徴です5)。
膝を強くひねったり、膝に過度な負荷がかかったりすると、半月板の損傷につながります。半月板損傷になると、膝の痛みや動かしにくさなどの症状が現れます。
半月板損傷について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
関連記事:【医師監修】半月板損傷とは?半月板の役割や治療法、予防法もあわせて紹介
スポーツ外傷を発症した際の応急処置6,7)
スポーツ外傷を発症した際、「RICE」と呼ばれる応急処置を施しましょう。RICEとは、以下の単語の頭文字をとった言葉です。
- 安静(Rest)
- 冷却(Ice)
- 圧迫(Compression)
- 挙上(Elevation)
ここでは、それぞれの応急処置の対応について解説します。
安静(Rest)
スポーツ外傷が発生した直後は、まずは安静を心掛けましょう。ケガをした部位に負荷がかかると、損傷が大きくなって症状が悪化する恐れがあります。例えば、足首を捻挫した場合は歩行を避け、腕や肩を痛めた場合はその部位を使わないようにすることが大切です。
症状の程度によって異なりますが、数日間は安静期間を設けたほうが良いでしょう。ただし、長期間の安静は筋力低下を引き起こす恐れがあるため、痛みが落ち着いたら少しずつ身体を動かすことが重要です。
冷却(Ice)
ケガをした直後は炎症反応が強いため、患部を冷やしましょう。冷却することで血管が収縮して血流がおさえられ、腫れや痛みの軽減につながります。反対に、患部を温めると炎症反応が助長され、症状が悪化する恐れがある点に注意しましょう。
冷やす方法としては、ビニール袋やアイスバッグに氷を入れて、患部に15〜20分程度当てます。このときに、凍傷を防ぐために直接氷を当てず、タオルに包んで冷やしましょう。
圧迫(Compression)
ケガをした部位の内出血や腫れを防ぐために、患部を圧迫しましょう。圧迫の方法としては、弾性包帯やテーピングを使用して、軽く圧迫気味に固定します。包帯がない場合は、バンダナや手ぬぐいなどでも代用可能です。氷で冷やしつつ、その上からタオルや包帯を巻いて、圧迫する方法もおすすめです。
ただし、圧迫が強すぎると血管や神経に悪影響が出る恐れがあるため、強く巻きすぎないように注意してください。皮膚の色や感覚に異常がないか定期的に確認し、しびれや皮膚の色の変化がある場合はすぐに緩めましょう。
挙上(Elevation)
挙上とは、ケガをした部位を心臓よりも高い位置に保つことです。高い位置に上げることで、重力の力で血液やリンパ液が患部に届きにくくなり、腫れの軽減が期待できます。足首や膝などの下半身のケガであれば、座るときや寝るときに足を高く上げるようにしましょう。腕や手のケガの場合は、三角巾や専用のスリングを使用して腕をつり上げます。
このように、RICEの処置によってケガによる症状の拡大を防げます。ただし、RICEはあくまで応急処置のため、痛みが強い場合は整形外科のある医療機関を受診しましょう。
スポーツ外傷に対する再生医療とは?
スポーツ外傷の治療において、再生医療が新しい選択肢として注目されています。再生医療とは、体内の再生能力を持っている組織や細胞を活用する治療法のことです。自分自身の組織や細胞を活用するため、副作用が起こりにくく、身体への負担が少ないのが特徴です。
また再生医療は、保存療法と手術療法の間を補完する治療法といえます。「保存療法では効果がないものの、手術を受けたくない」と言う方にとって、再生医療は適している可能性があります。ただし、すべての方に効果があるわけではなく、症状の程度によっては適応でないケースもある点には注意が必要です8)。
再生医療のメリット・デメリットについてもっと知りたい方は、以下の記事もぜひご覧ください。
関連記事:【医師監修】再生医療のメリット・デメリットとは?関節痛に対する再生医療についても解説
スポーツ外傷に対する再生医療の種類と適応
再生医療といっても、その種類はさまざまです。ここでは、スポーツ外傷に対して行われる再生医療の種類について解説します。
PRP(多血小板血漿)療法
PRP療法とは、血液中の血小板(けっしょうばん)を高濃度に濃縮した多血小板血漿を活用する治療法です9)。血小板には、組織の修復を促進する働きがあるため、人が持つ治癒力で復帰を目指せます。
PRP療法では、まず本人から採取した血液を特殊な装置で遠心分離し、血小板を抽出します。そして、濃縮された血小板を患部に直接注射して治癒力を促進させます。
おもにPRP療法が適応とできるスポーツ外傷は、以下のとおりです。
- テニス肘
- ゴルフ肘
- 野球肘
- 肩腱板損傷
- 足底腱膜炎
- 肉離れ
これらの症状に対して手術ではなく注射による治療を施すため、身体への負担が少なく、早期から日常生活やスポーツへの復帰が見込めます10,11)。
APS(自己たんぱく質溶液)療法
APS療法とは、PRP療法をさらに発展させた次世代の再生医療です9)。濃縮された血小板をさらに特殊な方法で処理することで、炎症をおさえるたんぱく質と成長因子を高濃度に抽出します。治療方法はPRP療法と同じように、抽出した成分を患部に注射します。
APS療法が適応できるスポーツ外傷は、以下のとおりです。
- 変形性関節症
- 骨壊死
- 軟骨炎(軟骨の炎症)
PRP療法が関節の外側にある組織の損傷に適しているのに対し、APS療法は関節内の病変に効果を発揮するとされています12)。
幹細胞治療
幹細胞とは、以下の性質を持っている細胞のことです13)。
- 自己複製能:自分と同じ細胞を作る能力
- 分化能:さまざまな種類の細胞に変化する能力
これらの性質のある幹細胞を用いて、損傷した組織の修復を図ります。幹細胞治療の大きなメリットは、組織そのものを再生させる可能性がある点です。
従来の治療では対応が難しかった損傷に対して、新しい選択肢となることが期待されています。この幹細胞の多様性から、ケガだけでなく、幅広い病気に対する治療が研究されています。ただし、基礎的・臨床研究で組織修復効果が報告されつつありますが、標準治療として確立するにはさらなる試験が必要とされています14)。
再生医療を行ったアスリートの成功事例
再生医療はプロスポーツ選手のケガからの復帰を早め、選手寿命を延ばす効果が期待されている治療法です。実際に、再生医療を受けてケガの回復につながった事例も多くあります。
例として、メジャーリーガーである大谷翔平選手や田中将大選手も、ケガをした際にPRP療法を受けています15,16)。PRP療法を実施した結果、比較的短期間での競技復帰を果たすこととなりました。
また、陸上選手に対して幹細胞治療を行った事例も報告されています。陸上で世界新記録を出した譜久里 武選手に対して、脂肪幹細胞を用いた治療が実施されました。この治療により関節の炎症や痛みが軽減され、選手寿命の延伸につながったとされています17)。
スポーツ外傷をともなった場合は再生医療による治療の検討を
スポーツ外傷には筋肉の損傷や関節の損傷など、さまざまな種類があります。ケガの種類によっては自然治癒が難しく、適切な治療を受ける必要があります。そしてケガの治療の新しい選択肢として期待されているのが、再生医療です。ぜひ今回の記事を参考にして、スポーツ外傷をともなった場合、再生医療による治療も検討してみましょう。
【医師からのコメント】
スポーツ外傷の治療選択肢はこの 10 年で大きく拡がりました。特に PRP や APS、自己由来間葉系幹細胞などの再生医療は、従来なら「保存加療か手術か」の二択だった場面に第三の選択肢を提供します。
しかしながら、エビデンスの成熟度は治療法により大きく異なります。PRP はテニス肘・腱板損傷などで中等度の効果が示唆される一方、APS や幹細胞治療は対象疾患が限られ、長期成績を検証する大規模試験も進行中です。実際の診療では「損傷部位・重症度・競技復帰までの猶予・費用負担・法的規制」を多角的に評価し、標準治療と再生医療を組み合わせて最適解を考えます。
読者の皆様には、目新しい治療名だけで選択するのではなく、最新の科学的根拠と専門医の総合判断にもとづいて治療方針を決めていただくことを強くおすすめします。
【参考】
1)日本スポーツ振興センター|スポーツ外傷・障害について
2)日本スポーツ整形外科学会|5.肉離れ
3)霞ヶ浦医療センター|腱板断裂(けんばんだんれつ)
4)日本整形外科学会|膝靭帯損傷
5)日本スポーツ整形外科学会|33.半月板損傷
6)國學院大學|捻挫の応急処置(RICE
7)日本スポーツ整形外科学会|3. スポーツ外傷の応急処置 (RICE処置)
8)東京女子医科大学|関節再生医療|人工関節
9)北里大学|再生医療(PRP療法・APS療法)
10)負傷したアスリートの疼痛緩和に対する多血小板血漿注射の有効性:ランダム化比較試験の系統的レビュー - PubMed
11)部分層腱板断裂に対する多血小板血漿の有効性:系統的レビュー - PubMed
12)重症膝関節症に対する自己タンパク質溶液注射の臨床成績は、軽症または中等症に比べて劣る | Scientific Report
13)京都大学アイセムス|幹細胞研究とアイセムス
14)筋骨格系疾患の治療における細胞療法 | 幹細胞トランスレーショナルメディシン | オックスフォード・アカデミック
15)中国労災病院|PRP/APS療法について
16)大谷翔平、10月に投球肘にPRP注射 - Yahoo!スポーツ
17)琉球大学|脂肪幹細胞を用いた「変形性関節症治療」 ~沖縄「スポーツ再生医療」の活性化を目指して~
記事監修者情報