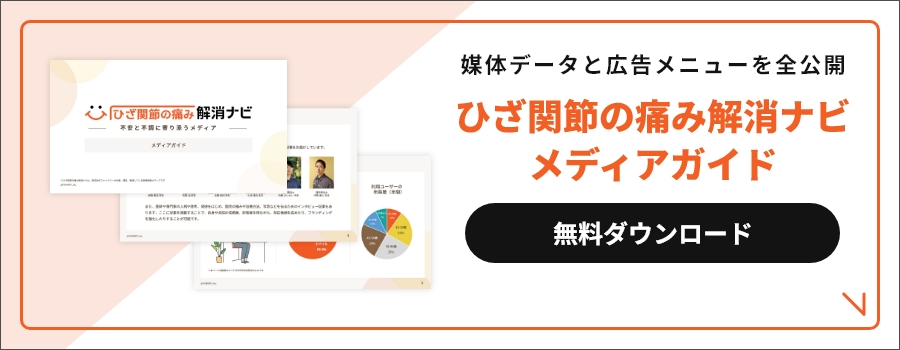コラム(開業医向けサイト)
難易度や活用法は?整形外科のための「医療経営士」について徹底解説
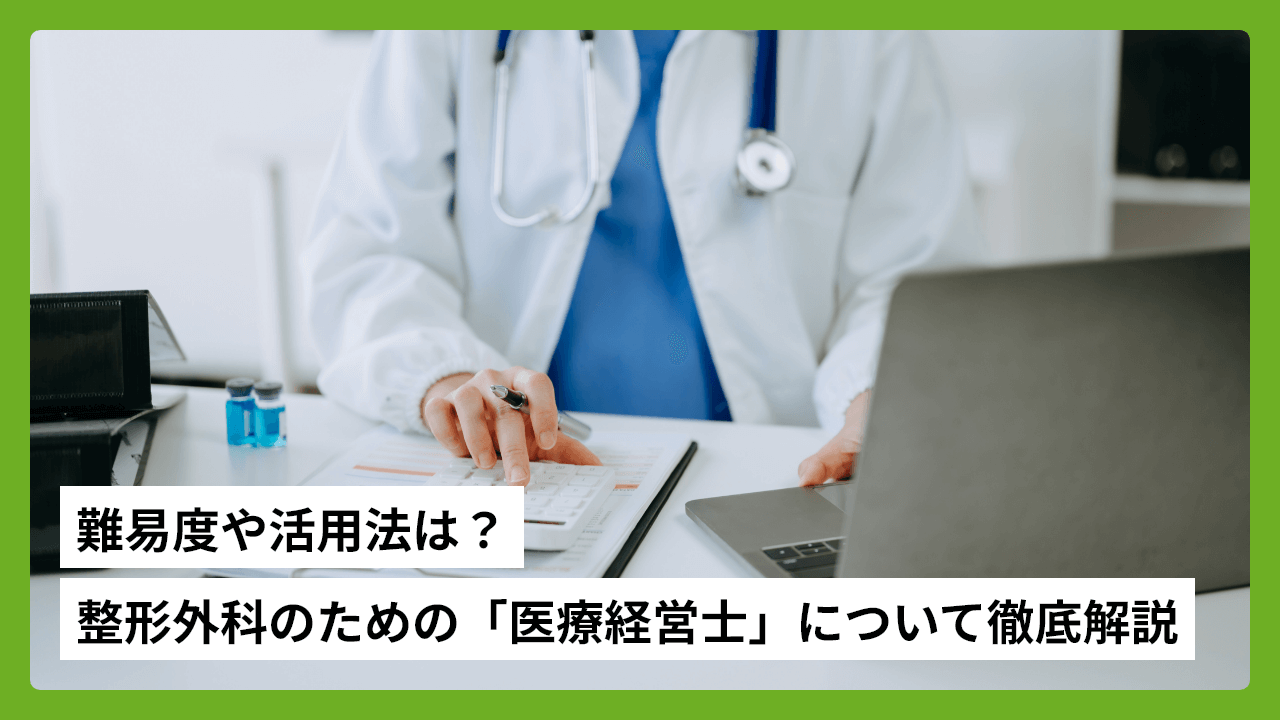
開業医は、院長が医療の提供に加えて医院の経営も行わなければいけません。しかし、医師としての専門知識は持っていても、経営に関する知識やスキル、経験が不足しているというケースは少なくないでしょう。そのため、開業医は「経営不在」と言われることもあります。医院を末永くかつ健全に運営していくのであれば、医療のスキルアップに取り組むだけでなく経営に関する知識やスキルを身につけることは不可欠です。
こうした医院運営に関する課題解決に役立つのが、医療の知識を持ち、医療機関の効果的なマネジメントが可能な人材育成を目的として創設された「医療経営士」の資格。医療の知識に加えて医療機関のマネジメントに関する知識を学び、資格を取得することは、その後の医院経営に大きなメリットとなります。また、将来的に開業医を目指している方にとっても役立つ資格と言えるでしょう。 本記事では、整形外科医院を経営している開業医の皆さまに向けて、医療経営士の資格について取得方法や難易度、取得するメリットなどを紹介します。
目次
この記事で分かること
- 医療経営士の資格の役割と取得方法
- 医療経営士の重要性
- 医院経営で取り掛かるべき4つのマーケティング施策
医療経営士とは?
医療経営士とは、一般社団法人日本医療経営実践協会が認定する民間資格であり、医療機関をマネジメントするうえで必要な「医療と経営双方の知識」「経営課題を解決する実践的な能力」を持つ人材育成を目的としています。
3級、2級、1級という3つの等級があり、飛び級のような制度はなく、2級・1級といった上位の資格を取得する場合、3級から段階的な取得が求められます。医療経営士の資格は、医師でなくても年齢や職種を問わず取得が可能です。看護師や薬剤師、病院やクリニックで働く事務スタッフ、医療関連企業の社員、医療業界を目指す学生など幅広い方を対象としています。
医療経営士の資格認定を受けるためには
医療経営士の資格認定を受けるためには、3級の認定試験に合格するだけでなく、日本医療経営実践協会の正会員として入会・登録申請を行わなければいけません。また、2級、1級を受験するにあたっても、協会の正会員であることが要件となっています。
試験に合格することで合格証明書が交付され、認定試験合格者として本協会の名簿に登録されますが、これらはあくまで合格した事実のみを管理するものであるため注意が必要です。
入会・登録の手続きは、試験合格後に登録料・年会費(各11000円)の納入と、個人正会員登録申請書・誓約書・履歴書の3点の書類を協会事務局へ送付することで完了。認定審査が行われ、問題がなければ医療経営士3級の認定証を受け取れます。正会員となることで名刺にも医療経営士であることを記載可能です。正会員への入会・登録は、合格証番号発行日から6カ月以内に行う必要があり、期間を過ぎると資格条件が失効するため早いうちに手続きを済ませましょう。
医療経営士資格は3年ごとに更新が必要であり、更新のためには等級ごとに定められた課題をこなし、申請書類の提出や更新手数料(11000円)の納入が求められます。
医療経営士の受験料
| 3級 | 9100円 |
| 2級 | 16000円 |
| 2級 第1分野または第2分野のみ | 14000円 |
| 1級 | 50000円 |
医療経営士3級~1級の試験内容と難易度
医療経営士は3級から1級で分けられ、等級ごとに出題形式や求められる知識などが異なります。
等級ごとの出題形式と出題数
| 出題形式 | 出題数 | |
| 3級 | 五肢択一・マークシート記入 | 50問 80分 |
| 2級 | 五肢択一・マークシート記入 | 第1分野・第2分野ともに各50問 80分 |
| 1級 | 第一次試験 短文記述形式 論文記述形式 | 短文記述形式 10問 論文記述形式 2問 各90分 |
| 第二次試験 口頭試問(プレゼンテーション形式) 個人面談 | 口頭試問と個人面談あわせて20分 |
等級ごとに求められる知識
●3級で求められる知識と難易度
3級は医療経営士の入門として位置づけられており、医師や看護師だけでなく、医療関連企業の従業員や医療分野を目指す学生なども対象となっています。協会推薦テキストの初級の内容から出題され、以下のような科目で構成されています。
出題科目
- 医療経営史
- 日本の医療政策と地域医療システム
- 日本の医療関連法規
- 病院の仕組み/各種団体、学会の成り立ち
- 診療科目の歴史と医療技術の進歩
- 日本の医療関連サービス
- 患者と医療サービス
- 医療倫理と臨床倫理
- 医療に関する最近の動向/時事
合格ラインは6割程度の得点を目安に、上位40~50%程度の成績優秀者の得点状況を考慮して相対的に評価されると言われています。受験者数や合格者数は一般社団法人日本医療経営実践協会の公式サイト上で公開されており、合格者率は実施回ごとに異なるものの、2022年~2024年では27%~35%ほどであり、決して楽に取得できる難易度ではないと言えるでしょう。
●2級で求められる知識と難易度
2級は、3級の知識をもとに、人材管理や財務会計、マーケティング、組織改革といった、より実践的な経営管理手法が問われます。現場の課題解決に直結した知識が求められ、医療機関における中間管理職やチームリーダー、医療経営コンサルタントなどが取得することを想定しています。
2級の試験は第1分野と第2分野で分けられているのが大きな特徴。両分野に合格して初めて2級合格となります。どちらかのみ合格した場合は、第1分野または第2分野の合格証明書の有効期限内であれば、不合格分野のみの受験が可能です。協会推薦テキストの中級の内容から出題され、以下のような科目で構成されています。
出題科目 第1分野
- 医療経営概論
- 経営理念・ビジョン/経営戦略
- 医療マーケティングと地域医療
- 医療ICTシステム
- 組織管理/組織改革
- 人的資源管理
- 事務管理/物品管理
- 病院会計
- 病院ファイナンス
- 医療法務/医療の安全管理
- 医療に関する最近の動向/時事
出題科目 第2分野
- 診療報酬制度と医業収益
- 広報・広告/ブランディング/マーケティング
- 管理会計
- 医療・介護の連携
- 経営手法の新戦略
- 多職種連携
- 業務改革・改善
- チーム医療と現場力
- 医療サービスの多様化と実践
- 医療に関する最近の動向/時事
一般社団法人日本医療経営実践協会の公式サイトで公開されている合格者率では、実施回ごとに異なるものの、2022年~2024年では27%~35%ほどであり、3級よりも合格率は大きく下がっています。
●1級で求められる知識と難易度
1級は、理事長や院長など医療機関の経営幹部や上級管理職を対象とした資格であり、組織全体の方向性を定める統合的かつ戦略的な能力が要求されます。1級試験は、第一次試験と第二次試験で分けられているのが特徴です。第一次試験では短文記述形式や論文記述形式、第二次試験ではプレゼンテーション形式での口頭試問や個人面接が行われます。協会推薦テキストの上級の内容が対応しており、出題範囲は以下のとおりです。
出題範囲 第一次試験
以下A、B、Cの分野から出題されそれぞれ短文記述形式で回答。
A.「病院経営戦略論(Ⅰ)」
- 病院経営戦略論
- バランスト・スコアカード
- クリニカルパス/地域医療連携
- 医工連携
B.「病院経営戦略論(Ⅱ)」
- 医療ガバナンス
- 医療品質経営
- 医療情報セキュリティマネジメントシステム
- 医療事故とクライシス・マネジメント
C.「病院経営戦略論(Ⅲ)」
- DPCによる戦略的病院経営
- 経営形態
- 医療コミュニケーション
- 保険外診療/附帯業務
- 介護経営
1級の合格基準では「『医療経営士1級』としてふさわしい能力および人格を有しているかどうか」があげられており、知識の有無だけではなく経営のトップとしての資質も問われます。一般社団法人日本医療経営実践協会の公式サイトでは、2022年~2024年の合格率は、第一次試験37.5~44.4%、第二次試験は60~80%ほどです。第二次試験の合格率が高いことから、論理的な経営戦略の文章化が求められる第一次試験が大きなハードルと言えるでしょう。
クリニックの規模や戦略で異なる資格取得の目標
どの等級の取得を目指すかは、クリニックの規模や戦略によって異なります。各クリニックの状況にあった資格取得を目指すことが大切です。「一人医師・小規模クリニックの院長」や「成長・拡大を目指す中規模クリニックの院長」といったケースで目指すべき等級の例を紹介します。
一人医師・小規模クリニックの院長の場合
一人医師や小規模クリニックでは、日々の運営を安定させることや院長にかかる業務の負担軽減が目標となるでしょう。そのために、院長自身が3級を取得し経営の全体像などを把握します。その後、自身で2級取得を目指すのも良いですが、医師としての業務と資格取得の勉強を両立するのは容易ではありません。そこで、費用などを医院がサポートし、意欲のある医師やスタッフに2級の取得を目指してもらいます。こうすることで、院長が診療に専念しながら、信頼できる業務執行責任者の育成が可能です。
成長・拡大を目指す中規模クリニックの院長の場合
成長・拡大を目指す中規模クリニックでは、経営力強化や新規事業などの成長戦力の推進が目標となるでしょう。そこでまずは、院長が1級または2級を取得し、より高度な経営戦略を学びます。同時に、事務長などそれに準ずるスタッフに2級、看護師長などのスタッフにも3級の資格を取得してもらうことで、経営層から現場まで全体に経営に関する意識を浸透させることが可能です。
医療経営士を取得するメリット
医療経営士の資格を取得することの主なメリットとして以下のようなことがあげられます。
経営者目線の獲得
開業医の多くで「経営不在」とされる中で、医療経営士の資格取得によって経営者目線を獲得できるのは最大のメリットと言えるでしょう。資格取得に向けた学習の中で、財務、人事、マーケティングといった医院の経営システムを理解し、経営者視点を持つ医師となることで客観的な意思決定が下せるようになります。会計士やコンサルタントの提案をただ鵜呑みにせず、対等に話し合い自ら評価・判断できるようになるのも大きな利点です。
スタッフが取得することでの組織力強化
医療経営士の資格は、院長だけでなくスタッフにも取得させることで、「経営パートナーへの成長」を促せます。日々の労務管理、経費のモニタリング、診療報酬請求の最適化、簡単なマーケティング活動といった業務をスタッフに任せられれば、より付加価値の高い診療行為や、分院展開、新規事業の検討といった戦略に集中できるでしょう。
また、資格を持ったマネージャーは院長と現場スタッフとの間に立ち、組織内のコミュニケーションを円滑にする効果も期待できます。院長の経営方針をしっかりと現場に伝え、現場の声を経営に生かすことができれば、スタッフの定着率や組織全体のパフォーマンス向上につながるのも大きなメリットです。
医療経営士が求められる背景
近年の医院経営を取り巻く環境は、物価高、AIの進化、働き手不足など、さまざま要因によって大きく変化してきました。そのため、医師個人で経営しているクリニックや診療所をはじめ、多くの医院が悩む以下のような経営課題を解決するために医療経営士という資格が求められるようになっています。
医院経営にかかるコストの高騰
医院経営には、賃料や医療機器の導入、スタッフの人件費などのコストがかかります。特に整形外科医院では、レントゲン、超音波診断装置、リハビリ機器などにかかる設備投資、リハビリスペースを確保できる物件の賃料、理学療法士や作業療法士の雇用など、ほかの診療科よりも高い固定費がかかるケースが少なくありません。また、近年では円安や物価高の影響で、さらなる費用の高騰ものしかかります。これらの高額な固定費がかかる中で利益を出すためには、財務、人事・労務管理、マーケティングといった効率的な医院経営が不可欠です。
優秀な人材の獲得競争
医師一人で診療やリハビリなど医療提供のすべてを行うのは難しいでしょう。より多くの患者数を確保するためには、医師や理学療法士や作業療法士といったスタッフを雇うのが一般的です。しかし、少子高齢社会となり労働者人口が減る中で、優秀な人材を確保することは難しくなりつつあります。また、機会に恵まれて優秀なスタッフを雇用したとしても、定着させるための労務管理や教育などの体制構築も重要です。
報酬改定による経営悪化
あらゆるコストの高騰に加えて、2年に1度行われる診療報酬改定は、クリニックの収益に大きく関わる外部環境の変化です。令和6年度の改定では、「従業員の賃上げ」「基本料金見直し」「DX対応システムの導入」などによる金銭的負担が増加した医院も少なくないでしょう。また、ベースアップ評価制度の見直しによる事務負担も無視できません。このような経営に影響を及ぼす外的要因に対応することも医院経営には欠かせないスキルです。
他医院との差別化や戦略が重要となっている
整形外科医院は、ほかの医院だけでなく整骨院や整体などもライバルとしてあげられます。ライバルが多い中で来院を促すためには差別化や集患・増患戦略が重要です。特に近年では、インターネットを活用して医院を探す人が増えており、ただ医療提供を続けるだけでは多くの患者を集めることが難しくなっています。そのような状況で、健全な医院経営を続けるためには、ほかの医院、整骨院、整体などとの差別化、ホームページやSNSを使った集患・増患戦略が重視されるようになっています。
医療経営士の資格を持つ外部の人材を雇うのも一つの手
医療経営士の資格は、医院の管理経営の中心となる院長が取得するのが望ましいと言えます。しかし、資格取得のためには相応の医療と経営の知識が求められる試験に合格しなければいけません。「日常の診療やクリニック経営といった業務を行いながら勉強時間を確保するのは難しい」という方も多いはずです。そのような場合は、資格を取得した外部の人材を雇い経営目線を取り入れることを検討しましょう。
医療経営士の資格は、医療関連サービスを提供する企業に勤務している人などでも取得できます。そのため、医療経営士の資格を持つ医療従事者やコンサルタントなどの人材を雇うのも一つの手です。院長は医療に集中しながら、経営の課題発見・解決、人事分野の強化を図れます。
医院経営で今すぐ取り掛かりたい4つのマーケティング施策
これまでは、特に集患や増患を意識しなくても、近隣の患者が受診しに来ることが多くありました。しかし、昨今ではWebで情報を集めて医療機関を選ぶ人が増えており、マーケティングによる集患・増患の重要性が高まっています。マーケティングは、数日や数ヶ月で劇的に効果が現れるわけではありませんが、先を見据えた医院運営をするのであれば欠かせない施策と言っても過言ではありません。こちらでは、比較的すぐに取り掛かれる4つのマーケティング施策を紹介します。SNSや医院ホームページなどを活用して、良好な医院経営を目指しましょう。
SNSでの発信
多くの人が利用しているSNSは、より広く医院の情報を伝えられる貴重なアクセスポイントです。適切なSNS運用によって、地域住民や潜在患者に身近に感じてもらえるのはもちろん、スタッフ採用などにも効果が期待できます。
運用の際は、各SNSの特徴に合った情報発信を行うことが重要です。リアルタイムな情報が発信できるXでは「臨時休診のお知らせや空き状況」など、FBでは「健康管理のアドバイスやセルフケア情報」、医院公式LINEでは「予約のリマインド、診療内容に関するFAQ、イベント告知」などが適していると言えます。
医院の強みを打ち出したホームページ制作
サイトを運用している医院も多いかと思いますが、適切な運用がされていなければ十分な効果は得られません。医院のホームページを作成する際は、「医院の専門性や強みをしっかりと打ち出す」「使いやすいサイト設計や動線」「ブログなどで健康に関する医院独自の情報発信」「地域の整形外科や提携病院、介護施設との情報連携」などを意識しましょう。
こうしたポイントを押さえることで、訪問者が医院の情報をキャッチしやすくなるのはもちろん、検索サイトやAIからの評価を得られるためSEOやLLMOにも効果的です。検索結果で上位に表示されたり、AI OverviewsなどAI検索で表示されたりするようになれば、より効果的なWeb経由での集患・増患が可能となるため、決しておろそかにはできません。
医院ホームページをしっかりと作りこむための時間やノウハウがないという場合は、Web制作会社などに依頼をすることも検討しましょう。
書籍の出版やメディアへの露出
書籍の出版や各種メディアへの露出も、医院の認知度や信頼度をアップさせる有効な手段です。顔写真が掲載されたインタビュー記事、健康情報記事の監修、専門知識を生かした書籍の出版などは積極的に取り組みましょう。インタビュー記事や監修した記事が掲載されたら、医院ホームページへのリンクをお願いすることでSEO的にも良い評価が得られます。また、記事掲載や本の出版を医院ホームページで実績として紹介することもユーザーからの信頼を得るのに効果的です。
GoogleビジネスプロフィールなどによるMEO対策
MEO対策とは、Googleマップなどの地図検索で自医院や施設の情報を上位に表示させるための施策です。「地域名 整形外科」などのキーワードで検索された際に、自医院のホームページが上位に表示されることで、優先的に多くの患者が医院情報に触れるようになるため集患効果が見込めます。よりローカルな商圏地域の情報として表示されるので、競合が少なく規模による差が小さいのもポイントです。具体的なMEO対策としては以下のようなものがあげられます。
Googleビジネスプロフィールの登録・オーナー認証
Googleビジネスプロフィールに登録とオーナー認証を行うことで、検索結果に表示される店舗情報の管理が可能になります。
適切なカテゴリ設定・NAP情報(店名・住所・電話番号)の統一
Googleビジネスプロフィールに登録する情報は正確かつ詳細に掲載しましょう。ビジネスカテゴリ、住所やマップピンの位置情報、診療時間、電話番号、ホームページURL、診療内容や設備など、複数の項目をしっかりと記載しましょう。
写真や動画を追加するなど情報を充実させる
写真や動画といった情報を掲載することで、ユーザーからの安心感や信頼感の獲得につながります。医院外観や内観、受付の様子、院長、スタッフなど、写真や動画を積極的に投稿しましょう。投稿する写真や動画は、「高画質で鮮明なもの」「過度な加工を避ける」といった点を意識するとより効果的です。また、投稿機能を活用して、新しい治療の開始や機器の導入、健康教室の実施情報など、医院からのお知らせを発信するのも露出の拡大につながります。
高評価や良い口コミの獲得と返信
実際に来院された方の口コミはMEO対策として非常に重要な要素です。単純に高評価を得ることはもちろんですが、正当な方法によって口コミや評価をしてもらうことも大切。なんらかのサービスの対価としてレビューを依頼するといった行為はガイドライン違反にあたるため注意しましょう。また、口コミに返信をすることで、患者とのコミュニケーションを重視していることをアピールできるだけでなく、医院の姿勢や院長の人柄などが伝わりやすくなります。
医院ホームページのSEO対策(適切な情報の掲載や地域サイトなどからの被リンク獲得)
MEO対策とSEO対策は別物ではありますが、関連付けられた医院ホームページの評価も評価指標のひとつとなっています。そのため、SEO対策にもしっかりと取り組むことが大切です。
【参考】:どこよりも詳しい!整形外科のための集患・増患・集客ガイド
医院経営の不安を解消する医療経営士
医療経営士の資格は「経営不在」とも言われる医院経営に関する不安解消に効果的な資格です。3~1級と等級が分かれており、上級になればなるほど難易度も高くなりますが、医院経営をするのであれば取得を検討しましょう。
医師免許を持っていない方でも取得できるので、院長、在籍医師、理学療法士などは1級や2級、そのほかのスタッフにも3級の資格取得を目指してもらうことで、医院全体の経営リテラシーアップも見込めます。より良好な医院経営を目指すのであれば、医療経営士の資格取得を検討すると同時に、Webにおけるマーケティング施策などを行いましょう。