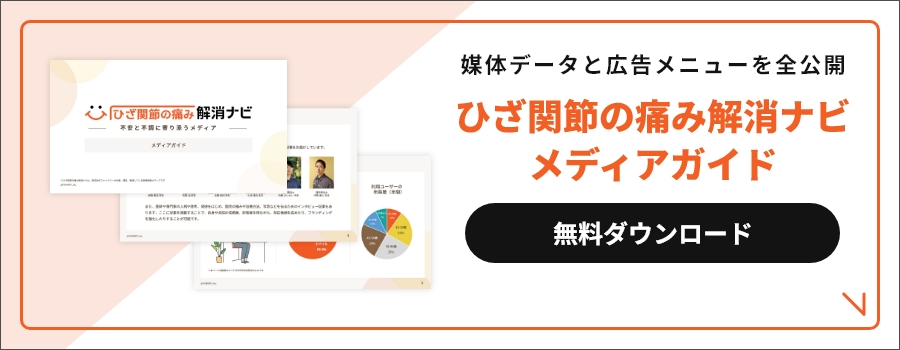コラム(開業医向けサイト)
【おすすめ9選】整形外科に向いている電子カルテメーカーを一挙紹介!

技術の発展が進み、多くの企業がデジタル化やAIの活用を進めています。こうした流れは、整形外科医院も決して他人ごとではありません。2024年度の診療報酬改定では、医療DX推進体制整備加算が新設されるなど、医院のDX化を推進する動きも活発になっています。
そのような流れの中で、まず考えたいのが電子カルテの導入です。電子カルテは、これまで紙だったカルテをデータ化し管理・活用をするシステム。さらに、現在提供されている製品の多くは、診療予約システム、AIによる文書作成アシスト、レセコン、オンライン診療、処方・検査オーダーなど、あらゆる医院業務をサポートしてくれる機能が搭載されています。
電子カルテの導入には、金銭的なコストはもちろん業務フローの変更や運用体制の構築といった負担が発生しますが、それに見合った大きなメリットがあるのも事実です。
本記事では、整形外科医院を経営している開業医の皆さまに向けて、電子カルテについて主な機能や種類、費用相場、メリット、おすすめのメーカーを紹介します。
目次
この記事でわかること
・クリニックで電子カルテを導入するメリット
・整形外科における電子カルテの選び方
・整形外科におすすめの電子カルテメーカー
電子カルテとは
電子カルテとは、これまで紙で管理されていた患者に関する臨床情報を電子データ化し一元管理するシステムです。診療記録の電子化だけでなく、受付や検査・処方のオーダー、処方、会計など、診療におけるあらゆるプロセスを管理できる統合プラットフォームとしての役割を果たしています。
2024年度の診療報酬改定では、医療DX推進が重視され、医療DX推進体制整備加算が新設されました。この算定条件に、電子カルテ情報共有サービスの活用体制を有していることが組み込まれるなど、多くの医院で電子カルテの導入・活用に取り組むことが求められています。
電子カルテの主な機能
メーカーや製品によって使用可能な機能は異なりますが、電子カルテの基本的な機能は以下のようなものがあげられます。
カルテ入力
患者の診療内容を記録する機能であり、患者の基本情報、主訴、病歴、アレルギー情報、診察所見などを管理する機能です。製品によっては、キーボード入力だけでなく、タッチペンによる手書き入力、音声認識によるテキスト入力などさまざまな入力方式があり、利用者の好みやワークフローの多様性に対応できるようになっています。
SOAP形式
多くの電子カルテシステムは、SOAP(Subjective: 主観的情報, Objective: 客観的情報, Assessment: 評価, Plan: 計画)形式に準拠して設計されています。臨床記録に論理的な枠組みを取り入れることで、明瞭性や一貫性のある記載が可能です。
テンプレートとセット登録
頻繁に遭遇する疾患や処置に関してはテンプレート作成が可能。また、頻用する処方、検査、処置の組み合わせをセット登録できる機能もあり、ワンクリックでのオーダーもできるようになります。同じようなデータ入力作業が削減でき、業務効率アップが期待できます。
過去履歴参照
患者の過去の診断、治療、検査結果など全診療履歴を、時系列で表示できます。患者の病状経過や長期的な変化を迅速に把握することが可能です。
処方オーダー
薬剤データベースから医薬品を選択し、処方箋を発行できます。薬剤名や薬効分類での検索も可能です。製品によっては、標準的な用法・用量を自動的に表示する機能がついているものもあります。
検査オーダー
検査部門や放射線部門などへの検査依頼も電子カルテから可能です。手書きの依頼箋が不要となり転記ミスも削減できます。
臨床意思決定支援 (Clinical Decision Support)
オーダーの発行時に潜在的な問題を自動的にチェックし、アラートを出してくれます。主なチェック項目としては以下のようなものがあります。
・患者のアレルギー情報
・薬剤間の相互作用や併用禁忌
・重複した処方や検査
有害事象につながりかねない医療過誤を未然に防ぐことが可能です。
医療文書作成支援
テンプレート機能や患者データ自動入力機能を活用して、紹介状、診断書、同意書などのさまざまな公式文書の作成を効率化できます。これにより、医師や事務スタッフの管理業務負担が大幅に軽減できるだけでなく、文書の品質確保にもつながります。
外部システム連携
電子カルテは、レセプトコンピューターや予約システム、検査機器・PACS、Web問診など院内のほかのシステムと連携が可能です。組織全体の中枢として医院でのあらゆる業務を包括的に管理できます。
電子カルテとレセプトコンピューター(レセコン)の違い
電子カルテは診療履歴など臨床情報を電子データで管理するシステムです。一方のレセプトコンピューター(レセコン)は、診療報酬明細書の作成が主な目的のシステムとなります。
これらは目的や用途が異なるシステムですが、電子カルテはレセコン一体型やレセコンとの連携ができるようになっているものがほとんどです。電子カルテとレセコンが連携することで、診療から会計までの手間を大幅に省くことができます。
既に導入しているレセコンを継続利用する場合はレセコンとの連携ができる電子カルテ、新規開業や電子カルテの導入とともにレセコンの乗り換えを考えている場合は一体型を選ぶのが良いでしょう。
電子カルテの種類
電子カルテは、大きく分けて「オンプレミス型」「クラウド型」「ハイブリッド型」の3つに分けられます。それぞれの特徴について紹介します。
オンプレミス型
オンプレミス型は院内にサーバーを設置し管理を行うタイプの電子カルテです。カスタマイズ性が高く、独自のワークフローや特殊な既存機器との連携も可能。インターネットに接続しない構成にすることで、外部からのハッキングなどの脅威にも強くなるほか、インターネット回線の状況に左右されずに安定したパフォーマンスが期待できます。一度設置してしまえば、維持費を安価に抑えられるのも大きなメリットです。
ただし、システム構築費やサーバー設置費がかかるため、初期費用が高額になる傾向にあります。維持管理を基本的に自己責任で行う必要がある点にも注意しなければいけません。
クラウド型
クラウド型はベンダーが管理するサーバーを利用してシステムを利用する電子カルテです。初期費用を無料から数十万円程度に抑えられるほか、システムの更新などの維持管理に関する手間も省けます。権限を持つ利用者であれば、インターネット環境があればどこからでも電子カルテにアクセスできるので、訪問診療などでも手軽に電子カルテを利用できるのが大きなメリットです。
ただし、オンプレミス型に比べてカスタマイズ性が低く、月額や年額での運用費が永続的にかかります。また、電子カルテを利用するためにはインターネット環境が必須になるため、回線の状況によっては利用が難しくなるのもデメリットと言えるでしょう。
ハイブリッド型
ハイブリッド型は、オンプレミス型とクラウド型の要素を組み合わせた電子カルテです。「医院にサーバーを置きながら、バックアップをクラウドにとっておく」などの構成がこれに当たります。2つの型の良いとこ取りができるので多くのメリットがある一方で、その分より多くのコストがかかります。導入の際は費用対効果を見極めることが重要です。
電子カルテ導入の費用相場
電子カルテ導入の費用はオンプレミス型とクラウド型で大きく異なります。
| クラウド型 | オンプレミス型 | |
| 初期費用 | 無料~200万円程度 | 2~10万円程度 |
| 月額費用 | 200~500万円程度 | 2~5万円程度 |
電子カルテの導入費用は決して安価ではありませんが、IT導入補助金などの補助金制度を活用することで負担を軽減できる可能性があります。ただし、補助金制度を利用するには一定の条件をクリアする必要があるほか、申し込み上限が定められているケースが多いため事前に確認をしておきましょう。また、制度の改正によって補助金額や条件が変更となることもあるため注意が必要です。
電子カルテの導入でかかる主な費用の内訳は以下のようになっています。
・ソフトウェア購入費
システム本体のライセンス費用。
・ハードウェア購入・設置費
サーバー(オンプレミス型の場合)、PC、タブレット端末、プリンター、スキャナーなどの機器代。
・設定作業費
院内ネットワークの構築、システムのインストール、各種設定作業にかかる費用。
・スタッフ研修費
操作方法のトレーニングにかかる費用。研修回数や日数によって変動。
・データ移行費
紙カルテのスキャンや既存のレセプトコンピューターからの患者基本情報・履歴の移行作業にかかる費用。
このほか、保守費用やサービス利用料、オプション費用などがランニングコストとして発生します。
電子カルテを導入するまでの期間目安
電子カルテの導入は、ただITツールを購入するというわけではなく、医院業務の改革プロジェクトと考えて計画的に進めることが重要です。そのため、選定から稼働までには半年から1年程度を見込んでおくと良いでしょう。電子カルテ導入までには以下のようなロードマップが例としてあげられます。
・フェーズ1 選定 稼働6カ月~1年前
電子カルテを導入するにあたり、まずは医院が抱えている課題や改善点を洗い出し「具体的な目的」を設定しましょう。目的を設定することで、必要な機能など優先順位を判断しやすくなるだけでなく、不要な機能を排除することで結果的に導入費用を節約できる可能性もあります。合わせて、導入費用とランニングコストの上限を決めておきましょう。
優先して取り入れる機能や予算が決まったら、ベンダーを調査し問い合わせ、製品デモンストレーションに参加して使用感や業務フローとの適合性を確認します。調査やデモンストレーションへの参加は手間や時間がかかりますが、選定における重要なプロセスであるため、複数のベンダーを比較することが大切です。
・フェーズ2 設計・構築 稼働3~6カ月前
導入するベンダーと製品が決まったら、正式に発注を行います。電子カルテの導入によって業務フローも大幅に変わることになるので、ベンダーと緊密に連携しながら受付、予診、診察、検査オーダー、処方、会計、次回予約など、診療に関わる一連の流れをシステムに合わせて運用設計しましょう。
基本設定、既存のシステムや紙カルテからのデータ移行には時間がかかるため、本稼働希望日から最低でも3~4カ月前までには発注をしておく必要があります。本稼働の1~2カ月前にはサーバーや端末など各種機器が納品・設置されます。
・フェーズ3 稼働準備・実行 稼働1~2カ月前
フェーズ2で設計した運用設計をもとにすべてのスタッフが稼働に向けて操作研修を受けます。また、本稼働までに実際の業務を想定したシミュレーションも行っておきましょう。この際に、問題点などを洗い出して運用フローの修正やマニュアルの作成を行います。
本稼働の1~2週間前には、シミュレーションの結果を踏まえて、ベンダーと医院で重大な課題や問題なく業務に臨めるかなどの最終確認を行い、問題がなければ稼働へと移行します。
本稼働後はトラブルの発生が予想されるため、ベンダーのサポートスタッフと連携しながら着実に運用しましょう。
・フェーズ4 改善 稼働後
電子カルテシステムの運用開始後は、定期的にスタッフからのフィードバックを収集し、設定変更や運用フローの細かな改善を継続的に進めることが大切です。導入して終わりではなく、継続的に改善を行うことで、医院にとって最適な電子カルテの活用を実現できます。
電子カルテを導入するメリット
紙のカルテに慣れている方にとって、業務フローの大きな変更を伴う電子カルテの導入は心理的な障壁を感じることもあるかもしれません。しかし、電子カルテを導入することには多くのメリットがあります。
業務効率の向上
情報管理に関する負担を大幅に軽減できるのは、電子カルテ導入の大きなメリットと言えます。紙のカルテでは時間や手間のかかる検索、搬送、保管、整理といった作業を劇的に効率化できます。また、電子カルテでは、書類作成、カルテ入力、レセプト(診療報酬明細書)作成も簡単に行えるため、医師はもちろんスタッフの負担軽減と時間創出につながるでしょう。
これらは、医院の抱える人手不足や長時間労働といった経営課題の解決に直結し、結果としてスタッフのワークライフバランス改善、離職率の低下、採用・教育コストの削減といった効果も期待できます。
ミスの削減
電子カルテを導入することで、医師、看護師、薬剤師、検査技師といった多職種間でシームレスかつリアルタイムな情報共有が可能になります。そのため、伝達ミスといったコミュニケーションのエラーも解消されるでしょう。また、活字化による判読性の向上、臨床意思決定支援システムによる警告は、医療ミスのリスクを大きく削減できます。
連携の強化
電子カルテによって、院内ではシームレスな情報共有による連携強化が図れます。また、院外においても患者情報をほかの医療機関へ迅速に共有することが可能です。院内・院外を問わずスムーズな連携が実現できるだけでなく、全国の医院と情報を共有し適切な医療を提供できるのは電子カルテの大きな強みです。
サービスと満足度の向上
電子カルテはただカルテをデータ化するだけではなく、受付、診察、会計のあらゆる業務を効率化できます。患者の待ち時間を短縮し質の高い医療の提供を実現することで、サービスと満足度を向上させ健全な医院運営にもつながります。
コストの最適化と経営分析
ペーパーレス化によって、紙カルテの保管庫として使用していたスペースを診療や待合室などに活用できるようになります。また、紙、ファイル、印刷にかかるコストを削減できるのもポイント。
さらに、電子カルテを利用し蓄積した診療データから、患者層の傾向、疾病の統計、時間帯別の混雑状況、処方や検査のコスト構造などを可視化し分析することで、開業医に不可欠な医院経営にも役立ちます。
整形外科で電子カルテ導入する際の3つのチェックポイント
整形外科医院で電子カルテを導入する際にチェックしておくべき3つのポイントを紹介します。
画像検査を考えたPACS連携
整形外科では、レントゲン、MRI、CTなどで撮影した画像を見ながら診察する場面も多くあります。そのため、電子カルテとPACS(医用画像管理システム)との連携はチェックしておきたいポイントです。診察室と読影室の行き来やアプリの切り替えをすることなくカルテで画像を確認できれば、診療の効率アップに大きく役立つでしょう。
また、単純な画像表示ではなく過去の画像との時系列比較、画像への注釈、スマートフォンで撮影した創部や可動域の記録画像を簡単に取り込める機能などが搭載されている製品であれば、より診療の質と効率を高めることも可能です。
リハビリテーション部門との連携
リハビリテーションが収益と患者ケアの中心的な役割を担っているという整形外科医院も少なくないはずです。診療とリハビリテーションの連携を高める上で、治療計画書、理学療法士の記録、患者の進捗状況などを体系的に管理できるリハカルテ機能は大きな役割を果たします。
合わせて、予約システムと電子カルテを連携させることで、療法士や治療機器の効率的な予約管理ができるようになり、患者の待ち時間短縮やスタッフ稼働率の最適化も目指せます。
描画機能の使いやすさ
解剖学的な図(シェーマ)は整形外科診療において重要な要素と言えます。だからこそ、電子カルテにおけるシェーマへの入力のしやすさはしっかりと確認しておきたいところ。「入力が手間ではないか」「納得のいく所見を書き込めるか」はデモンストレーションの際に実際に使用しておきましょう。
整形外科におすすめの電子カルテメーカー9選
こちらでは、整形外科におすすめの電子カルテメーカーを9社ピックアップし紹介します。
ウィーメックス株式会 - Medicomシリーズ・きりんカルテ・Open-Karte Cloud
ウィーメックス株式会社は、長年にわたり市場をリードしてきたトップブランド。2023年には富士フイルムヘルスケアシステムズ株式会社の電子カルテ・レセプト関連事業を取得しました。代表的な「Medicomシリーズ」をはじめ、利用料無料のクラウド型電子カルテ「きりんカルテ」、有床診療所・中規模病院向けクラウド型電子カルテ「Open-Karte Cloud」など、さまざまな電子カルテ製品を展開しています。
価格は競合製品よりも高価な傾向にありますが、累計217,000件以上の導入実績を踏まえて設計された使いやすいUIや独自のAI自動算定機能、157ものサポート拠点を有するなど、大手電子カルテメーカーならではの機能やサポート体制が整っているのが特徴のひとつです。
エムスリーデジカル株式会社 - M3 Digikar
エムスリーデジカル株式会社は、医療情報サイト「m3.com」を運営するエムスリーグループの電子カルテメーカー。親会社であるエムスリーが持つ医師ネットワークを背景に、クラウド型電子カルテ市場で高いシェアを誇ります。
提供する電子カルテ「エムスリーデジカル」は、AIによるオーダーや病名の自動学習機能、iPadを活用したシェーマ手書き機能、保険診療と自由診療の容易な切り替えなど、必要な機能を搭載しながら比較的低コストなのが大きな魅力。初期費用0円、月額利用用11,800円(ORCA連動型)からという価格で導入が可能です。新機能の追加や改善などのアップデートが頻繁に行われるのも特徴のひとつと言えます。
ただし、導入3年目以降、月の受付回数が1,000件を超えると1001件目以降の来院1回あたり1点分(10円)が月額料金に加算されるため、患者数の多いクリニックでは総コストが変動する恐れがある点に注意しましょう。
株式会社EMシステムズ - MAPs for CLINIC
株式会社EMシステムズは調剤・医科・介護/福祉を軸に、医療機関へのシステム提供を行うメーカーです。電子カルテ「MAPs for CLINIC」では、ほかの製品ではオプションになりがちなWeb予約などの機能を標準で搭載し、オールインワンで使えるコストパフォーマンスの高さが特徴。「リハビリ支援機能」や「レントゲン撮影のオーダー入力支援機能」も含まれているので、整形外科医院での大きな活躍が期待できます。
ネットワーク停止時も自動で回線を切り替えて継続利用が可能、土日祝を含めた365日体制でサポートが受けられるなど、いざというときも安心の体制が整っているのもポイントです。
セコム医療システム株式会社 - ユビキタス電子カルテ・セコムOWEL
セコム医療システム株式会社は、防犯・セキュリティサービスで知られるセコムグループのメディカル事業を手掛ける企業。電子カルテ「ユビキタス電子カルテ」は、セコムの技術を活用したセキュリティ体制や、手術・術後管理を含む有床診療所のワークフローに強いのが大きな特徴です。リハビリシステムとの接続も充実しているので、整形外科領域でも価値を発揮してくれます。
統一患者ID機能を搭載しており、系列の診療所、病院、介護施設などの間でシームレスな患者情報の共有も可能。手術や入院設備、系列のある医院では、有力な選択肢となるでしょう。
在宅クリニック・無床診療所向けのシンプルな電子カルテ「セコムOWEL」も提供しているので、医院の規模に合わせて選択できます。
株式会社湯山製作所 - BrainBoxシリーズ
株式会社湯山製作所は、製剤機器や薬品管理システム、分包機などの医療機器を手掛ける大手メーカー。ユヤマ製の調剤機器や院内設備との連携が大きな強みと言えます。
オンプレミス型とクラウド型の2タイプの電子カルテを提供しており、医院に合わせて選択が可能です。オンプレミス型では、AIによるオーダーの提案や豊富な医薬品総合データベースを搭載。クラウド型ではAIによるWeb問診機能や、他院の医療統計、クリニック情報と自院の情報を比較できる経営支援機能が利用できます。
電子カルテや周辺機器に精通したスタッフによる手厚いサポートが受けられるのも大手医療機器メーカーならではの特徴と言えるでしょう。
株式会社DONUTS - CLIUS(クアリス)
株式会社DONUTSは、電子カルテのほかに配信アプリやゲームバックオフィス支援システムなども手掛けるIT企業。電子カルテ「CLIUS」の特徴として、 医師の目線の動きまで考慮して設計されたユーザーフレンドリーなインターフェース、AIによるオーダー推薦機能や自動学習機能などがあげられます。オンライン診療にも標準で対応しているのもポイントです。
電話サポート、メールサポート、遠隔サポートとサポート体制も充実。最も安価なプランでは、初期費用0円、月額19,800円(電子カルテ+レセコン)という価格で導入ができます。
株式会社ダイナミクス - ダイナミクス
電子カルテ「ダイナミクス」は、経費削減・業務効率化・診療の質の向上を目的として、内科医によって開発されたシステム。契約ユーザー限定でプログラムソースが公開されており、ITの知識があれば自院のニーズに合わせた自由なカスタマイズができるのが大きな特徴です。また、公式から「レセプト分析・集計ツール」「順番待状況表示ツール」「整形外科リハビリ集計」などの無料のオプションツールも提供されています。
オンプレミス型でありながら、初期費用220,000円~、月額料金13,200円~と安価に導入が可能なのもダイナミクスの特徴。ITの知識があるのであれば、高いカスタマイズ性のあるダイナミクスは魅力的な製品と言えるでしょう。
株式会社メドレー - CLINICSカルテ・MALL
株式会社メドレーは、医療ヘルスケア分野の人材採用システムや医療機関へのシステム提供を行うメーカーです。クラウド型電子カルテ「CLINICSカルテ」は、Web予約、Web問診、診療、会計、レセプト作成といった業務フローを一元管理できるのが特徴。株式会社メドレーが提供する患者向けアプリ「CLINICS」と連携して、オンライン診療、キャッシュレス決済、メッセージ送信などもできます。
受付から経営分析、患者の利便性・エンゲージメント向上までを担ってくれるため、医院の新規開業の際はもちろん、医院経営の改善を図る目的で電子カルテの導入を検討している場合も選択肢に入る製品と言えるでしょう。
富士通株式会社 - HOPEシリーズ
HOPEシリーズは、大手総合電機メーカーである富士通が提供している電子カルテです。新規開業医向けの「HOPE LifeMark-TX Simple type」や有床診療所にも対応の「HOPE LifeMark-SX」など、さまざまなバリエーションの製品を提供しています。細かな機能や性能は製品ごとに異なりますが、歴史ある大手電機メーカーのブランド力や経験に裏打ちされた信頼性と技術力が特徴。また、全国に拠点を持つ販売代理店の強力なサポートが受けられるのも魅力のひとつです。
政府が推進している医療DXや国際的な医療情報交換の標準規格「HL7 FHIR」への対応にも積極的に取り組んでいます。将来を見据えた電子カルテの導入を考えるのであれば、非常に有力な候補となるはずです。
まとめ
電子カルテは、紙カルテのデータ化にとどまらず、受付、診療、オーダー、会計、処方など医院でのあらゆる業務の効率化や安全性・医療の質の向上に大きく貢献してくれるシステムです。人材不足の解決や患者サービスの向上にもつながり、結果として良好な医院経営が実現できる可能性も十分に考えられます。
電子カルテを導入する際には、金銭的なコストだけでなく、メーカーや製品の選定、業務フローの変更、運用に関する教育といった負担が発生します。そのため、導入を後回しにしてしまうケースも少なくないでしょう。しかし、政府が医療DXを推進していることを考えれば、電子カルテの導入は必須と言っても過言ではありません。
まずは、電子カルテの特徴やメリットを知り、将来にわたって良好な医院経営を続けるための一歩を踏み出しましょう。