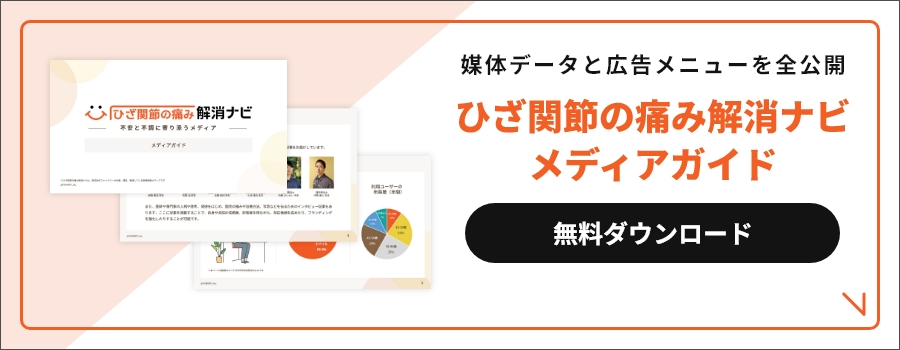コラム(開業医向けサイト)
【2026年版】整形外科クリニックのためのSNS活用術|Instagram・X・note・YouTube・LINE公式をどう使う?
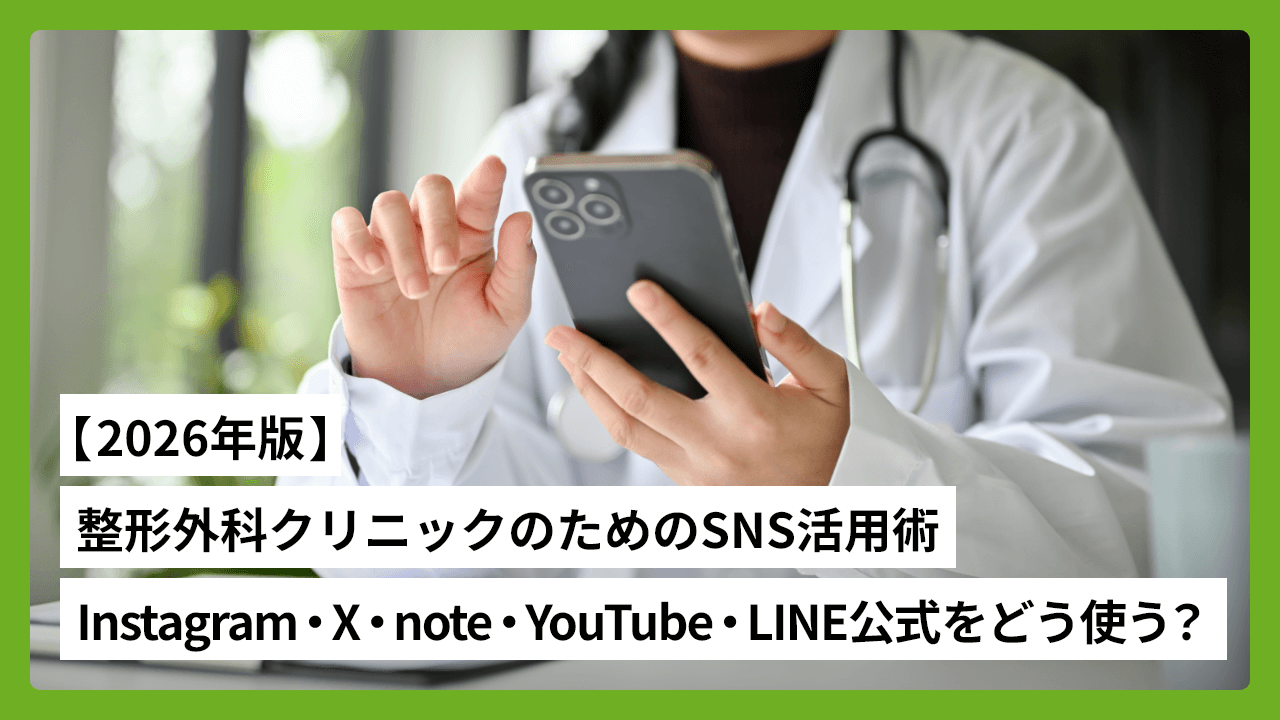
近年、整形外科クリニックの集患でSNS活用が注目されています。従来のチラシやホームページだけでの集患では限界があり、InstagramやX、YouTube、LINE公式などを駆使した情報発信が、新規患者さまの獲得や地域での信頼構築に大きく貢献する時代となりました。
しかし、「どのSNSを使えば効果的か」「何を発信すれば患者さまに届くか」と悩む医師も少なくありません。とくに、治療内容や症例の情報を安全に、かつ法的に正しく発信するには、専門的な知識と運用ノウハウが不可欠です。
本記事では、2026年最新の整形外科クリニック向けSNS活用術について、各SNSの特徴から活用方法、成功事例、注意点、効果測定の方法まで網羅的に解説します。これからSNSを導入するクリニック、そして運用効果が得られていないクリニックの双方に役立つ実践的な内容です。
目次
この記事でわかること
・整形外科クリニックにおけるSNS活用の最新動向と公的データ(総務省・厚労省など)
・各SNS(Instagram・X・YouTube・LINE・note)の特徴と最適な活用戦略
・医療広告ガイドラインに基づく安全な情報発信のポイント
・整形外科クリニックのSNS成功事例と成果分析
・KPI設定・効果測定・改善の方法(Google AnalyticsやSNSインサイト活用)
・患者さまとの信頼関係を築くための双方向コミュニケーション手法
整形外科クリニックにおけるSNS活用の重要性
整形外科クリニックでのSNS活用は、単なる情報発信の手段ではなく地域認知の向上や患者さまとのコミュニケーションのツール、専門性のアピールなど、経営戦略の一環として捉えることが重要です。
SNSを活用すれば、従来の広告手法では届きにくい若年層やデジタル世代の患者さまにも情報を届けることが可能であり、地域医療における存在感を高める手段としての効果も期待できます。
10~40代のデジタル世代にリーチしやすい
総務省の「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査(令和3年度)」によると、SNS利用率は10〜40代で8割を超え、医療機関選びにもクチコミ・SNS情報を参考にする傾向が強まっています。
また、YouTubeの利用率が高く、10~40代で90%を超えています。
信頼できる情報を取得するため動画を視聴する傾向があり、クリニックがSNSを通じて正確な医療情報やリハビリ指導、専門領域の特徴を発信することは、自院の認知向上と信頼形成の両面で効果を発揮します。
さらに、医療機関のICT活用を推進する厚生労働省の方針でも、地域連携や患者さまとの情報共有の観点から、SNSなどのデジタルツールを活用した発信・連携が奨励されています。SNSはこの流れの一環として、「地域医療のハブ」となる整形外科クリニックが、地域住民と継続的に関係を築く仕組みとして機能し得ます。
【参考データ】
令和3年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査|総務省
SNSの活用は集患や宣伝に効果的
近年は、来院前にクリニックの雰囲気や医師の人柄をSNSで確認する患者が増えています。治療方針やリハビリの様子、院内設備などを写真や動画で発信することで、初診前の不安を和らげ、来院につながるケースも多く見られます。とくに、症状別の解説やスタッフの日常など、患者目線の情報発信は信頼感を高め、地域での口コミ拡散にも効果的です。
また、SNSの活用は単なる集患施策ではなく、「医療の見える化」にもつながります。院内リハビリの取り組み紹介、学会発表の報告、地域イベントへの協力などを発信することで、クリニックの姿勢や専門性が伝わりやすくなります。
実際に、SNSを積極的に活用している整形外科では、患者満足度や地域評価の向上、リクルート面での認知向上につながった例も見られます。
整形外科クリニックに適したSNSの選定と活用戦略

SNSはそれぞれ異なる特徴を持つため、目的やターゲットに合わせたプラットフォームの選択と運用が不可欠です。主なSNSの種類は以下の通りです。
・Instagram
・X(旧Twitter)
・note
・YouTube
・LINE公式アカウント
ここでは各SNSの強みと活用ポイントを紹介します。
① Instagram:視覚的な情報発信と患者さまとの信頼構築
・ビフォーアフターの症例写真やリハビリ動画で治療効果を直感的に伝える
・ストーリーズでクリニックの日常やスタッフ紹介を配信
・ハッシュタグで地域密着型の検索に対応
Instagramは画像や動画で視覚的に情報を伝えることができ、とくに関節治療やリハビリなど動きがわかるコンテンツと好相性です。
ほかにも、治療のビフォーアフターやリハビリ動画を投稿することで、患者さまに治療効果を直感的に理解してもらえます。ストーリーズを活用すれば、クリニックの日常やスタッフの紹介などを通じて親近感を持ってもらうことも可能です。こうした運用で、患者さまに親近感を与えることができ、来院の心理的ハードルを下げる効果も期待できます。
②X(旧Twitter):リアルタイム情報発信と双方向コミュニケーション
・診療時間変更やキャンセル空き情報を速報で発信
・患者さまからの質問に迅速に対応することで信頼性向上
・専門的な医療情報や生活習慣のアドバイスも発信可能
Xは速報性に優れ、緊急性や短期間で伝えたい情報の発信に適しています。例えば、診療時間の変更や診察の空き情報などをリアルタイムで発信できる点が強みです。また、リツイートやコメント機能を活用した双方向コミュニケーションを実現すれば、地域内での信頼性や再来院率の向上、情報拡散も期待できます。
③note:専門的な医療情報の発信
・治療法やリハビリ方法、セルフケア記事の執筆
・教育コンテンツとしての活用
・SEO効果により検索経由の流入増加
noteは文章中心のSNSで、長文コンテンツや専門性の高い情報発信に向いています。患者さまが検索して知りたい情報をまとめることで、クリニックの信頼性向上や新規患者さま獲得に貢献します。
また、SEO(検索エンジン最適化)を意識したキーワード設計で記事を作成すれば、検索経由で新規患者さまを獲得することも可能です。
④YouTube:視覚と音声での治療解説に最適
・手術手順や治療法を動画で解説
・患者さまインタビューや症例紹介を公開
・定期更新でチャンネル登録者を増やす
動画投稿プラットフォームのYouTubeでは、手術手順や治療法の動画を通して視覚的に治療内容を解説できます。動画は文章や静止画より理解度が高く、患者さまの不安軽減にもつながります。遠方からの患者さまやリハビリ指導にも活用できる点が魅力です。
⑤LINE公式アカウント:予約・フォローアップに活用
・予約受付やリマインダー送信
・治療後フォローや健康情報の配信
・自動応答と個別対応のバランスを意識
LINEは幅広い世代に広く使用されているツールで、患者さまとの直接的なコミュニケーションができる点に強みがあります。
クリニックのLINE公式アカウントを運用することで、予約受付やリマインダー送信、治療後フォローなどに利用でき、患者さまとの直接的なコミュニケーションを効率化できます。患者さまの利便性向上と満足度向上に直結する運用が可能です。
各SNSの強みと活用ポイント
| SNSプラットフォーム | 主な特徴 | 活用目的 | 向いている発信内容 |
| 写真・動画中心のSNS。美容・健康領域との親和性が高い | クリニックの雰囲気や治療内容の「見える化」 | ビフォーアフター写真、リハビリ動画、スタッフ紹介、ストーリーズ配信 | |
| X(旧Twitter) | 短文・速報型の投稿が中心。拡散力が高い | 診療時間変更・臨時情報などの迅速な周知 | 休診案内、急なキャンセル空き情報、医療ニュース共有 |
| note | 長文・専門記事投稿に適したプラットフォーム。SEO対策により検索流入も狙える | 専門的な医療知識・教育コンテンツの発信 | 治療法・セルフケア解説、再発予防の知識記事 |
| YouTube | 視覚・音声で伝える動画SNS。説明力と専門性が高い | 手術・治療解説や院内紹介による安心感醸成 | 手術解説動画、患者さまインタビュー、設備紹介 |
| LINE公式アカウント | 生活に密着したコミュニケーションツール | 予約管理、リマインダー、フォローアップ | 自動応答メッセージ、治療後ケア案内、健康情報配信 |
活用目的に応じて、最適なプラットフォームを選択・運用することで患者さまとのコミュニケーションも円滑になり、リピーターの獲得や顧客満足度の向上につながります。
また、InstagramやYouTubeなど視覚的な情報発信で認知・信頼を高め、来院後は LINEで再診のお知らせや定期フォローを行うといったようにSNS単体よりも複数のアカウント運用による相乗効果で、他院との差別化・効率的な集患が期待できるでしょう。
具体事例で学ぶSNS活用術
ここでは、実際に整形外科クリニックで成功しているSNS運用の事例を紹介します。各事例では「どのようなSNSで」「どんな目的で」「どんな効果を上げたのか」を整理し、今後のSNS戦略のヒントとして活用できるようまとめています。
成功事例1:Instagramで症例紹介とリハビリ動画
背景:若年層や女性患者さまへの認知向上を目的にInstagramを導入。
施策:膝関節症やスポーツ障害のリハビリ動画、症例写真(患者さま同意済)を短尺で投稿。
「#リハビリ」「#膝の痛み」「#地域名」などのハッシュタグを活用し、地域内検索からの流入を促進。
成果:動画再生数の増加により地域での知名度が向上。初診予約数が前年比15%増加。
ポイント:
・投稿前に必ず患者さま本人の同意を文書で取得(医療広告ガイドライン遵守)
・医師や理学療法士が出演することで、信頼性・専門性を演出
・ストーリーズで「日常の診療風景」も発信し、親近感を醸成
成功事例2:Xで診療情報のリアルタイム発信
背景:外来患者さまから「当日の診療状況を知りたい」との要望が多く、即時性のあるSNS導入を検討。
施策:診療時間変更・キャンセル空き枠・季節ごとの注意喚起(例:転倒事故防止など)を定期投稿。
成果:患者さまがリアルタイムで最新情報を確認できるようになり、キャンセル枠の再予約率が約20%向上。
ポイント:
・医師・スタッフ共通の運用ルールを設け、誤情報発信を防止
・リプライでの質問対応により、再来院やフォロワー数増につながる
・定期的に「#整形外科」「#地域医療」などのハッシュタグ活用を行い、検索にヒットする工夫も
成功事例3:YouTubeで治療解説動画公開
背景:患者さまが「手術内容が不安」「治療方針を理解したい」と感じる声が多かった。
施策:医師自らが出演し、関節鏡手術の手順やリハビリの進め方を図やモデルを使って解説。患者さまインタビュー動画や「治療の前に知っておきたいポイント」もシリーズ化。
成果:動画の総再生数が10万回を超え、遠方からの問い合わせやセカンドオピニオンの増加につながった。
ポイント:
・専門用語を避け、誰でも理解できる語り口で解説
・概要欄にクリニックサイトや予約ページをリンク
・更新頻度を月1回ペースで維持し、チャンネル登録者を安定的に増加
成功事例4:LINE公式で予約・相談を効率化
背景:電話予約や再診調整の負担が大きく、スタッフの業務効率化が課題だった。
施策:LINE公式を導入し、
・予約受付(自動応答+スタッフ確認)
・リマインダー配信
・術後フォローアップや健康コラムの配信
を実施。
成果:電話対応件数を30%削減し、満足度アンケートで「連絡が取りやすい」との回答が増加。
ポイント:
・高齢の患者さまにも使いやすいメッセージテンプレートを整備
・配信時間を診療時間外に設定し、負担を軽減
・定期的にLINEアンケート機能で患者さまのニーズを把握
成功事例5:noteで医療知識や予防法を発信
背景:地域住民から「自宅でできるケアを知りたい」との声があり、教育的コンテンツを発信。
施策:膝痛予防のストレッチ法、転倒防止トレーニング、加齢に伴う関節変化などの記事を定期更新。
成果:Google検索で上位表示され、検索経由の新規来院が増加。また、地域医療機関や介護施設からも記事が引用され、専門性の認知が拡大。
ポイント:
・記事タイトルに「整形外科」「リハビリ」「膝痛」などのSEOキーワードを挿入
・図解や写真を入れて読みやすく
・note内リンクで関連記事を回遊させ、読者滞在時間を向上
各SNSは特性が異なり、「目的に応じて組み合わせて運用」することが成功のカギです。Instagramで“認知”、Xで“リアルタイム発信”、YouTubeで“理解促進”、LINEで“関係維持”、noteで“専門性訴求”というように、役割を明確化した運用が成果につながります。
SNS活用における注意点とリスクマネジメント
SNSを活用することで地域認知の向上や患者さまとのコミュニケーションを促進できますが、医療機関としては信頼性・安全性の確保が最優先です。公的情報や医療広告ガイドラインを踏まえ、以下のポイントを押さえて運用しましょう。
医療広告ガイドラインの遵守
・医療法および厚生労働省「医療広告ガイドライン」に従い、誇大表現や根拠のない治療効果の表示を避ける
・SNS投稿で症例写真や治療実績を紹介する場合は、患者さま本人の同意を文書で取得(個人情報保護法にも準拠)
・「絶対に治る」「〇〇%の成功率」などの表現は原則禁止
【参考データ】
医療法における病院等の広告規制について |厚生労働省
個人情報・プライバシー保護
・患者さまの氏名や顔写真を使用する場合は必ず同意を取得
・同意書にはSNSでの使用範囲、期間、第三者提供の有無を明記
・匿名化・モザイク加工などの方法で個人特定を防止
【参考データ】
総務省|電気通信消費者情報コーナー|電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドライン
運用体制とポリシーの策定
・投稿内容やコメント対応ルールを明文化したSNS運用マニュアルを作成
・運用担当者に対する教育・研修を定期的に実施
・投稿前の事前承認フローを設け、誤情報や不適切投稿のリスクを低減
ネガティブコメント・クレーム対応
・SNS上の否定的なコメントや口コミも対応の対象として、標準化された対応フローを整備
・公的機関や医師会の推奨する「クレーム対応マニュアル」を参考に対応
・個人情報の保護を前提に、公開コメント・非公開メッセージでの対応を使い分ける
SNS運用は、患者さまにとって有益な情報発信ができて利便性が高い反面、リスクも伴います。医療情報を発信する場合は、医療広告ガイドラインを遵守し、患者さまのプライバシーを保護しつつ、必要な同意を取得することが前提となります。ネガティブコメントや口コミへの対応も、基本的なクレーム対応の知識と、適切な対応フローの整備が重要です。
【参考データ】
苦情対応ハンドブック 第 2 版 国立大学附属病院医療安全管理協議会
安全な情報発信のチェックリスト
SNS運用を行う際は、担当者の教育や運用ポリシーの策定を行うことが求められます。あらかじめ、投稿内容や対応方針を事前に整備することで安全な運用が可能になります。SNSで安全に情報発信するためのチェックリストは以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
| 投稿内容の確認 | 治療効果や症例紹介が医療広告ガイドラインに適合しているか |
| 個人情報保護 | 顔写真や氏名を使用する場合、同意書を取得済みか |
| 投稿前承認 | 医師または管理者による確認済みか |
| コメント対応 | ネガティブコメント対応フローが整備されているか |
| 定期研修 | 運用担当者が情報発信・個人情報保護・クレーム対応を理解しているか |
SNS運用の具体的リスク事例と対策
SNSは便利な情報発信ツールですが、運用方法を誤ると医療機関の信用低下や法的トラブルにつながる可能性があります。ここでは、整形外科クリニックで実際に想定されるリスクと、その具体的な対策例をまとめました。
個人情報漏えいのリスク
| リスク事例 | 内容 | 対策 |
| 患者さまの症例写真や顔写真を許可なく投稿 | 患者さまの個人情報が特定され、プライバシー侵害につながる | 投稿前に文書による同意を取得。必要に応じてモザイク加工や匿名化。総務省の個人情報保護ガイドラインに準拠 |
| 患者さまの治療履歴や診療内容を詳細に記載 | 特定の患者さまが識別される | 症例紹介は統計情報や一般的な症状に留め、個人が特定されない表現にする |
誤情報・誇大広告のリスク
| リスク事例 | 内容 | 対策 |
| 治療効果を過大に表現 | 「必ず治る」「〇〇%成功」など、医療広告ガイドライン違反の表現 | 厚労省「医療広告ガイドライン」に準拠した表現に修正。根拠となる学会論文や統計データを併記 |
| SNS担当者が誤情報を投稿 | 専門知識不足により、患者さまに誤解を与える | 投稿前に医師または管理者による承認フローを設定。運用マニュアルでチェック項目を明文化 |
ネガティブコメント・炎上リスク
| リスク事例 | 内容 | 対策 |
| 治療に不満を持つ患者さまの投稿が拡散 | SNS上で炎上し、クリニックの信頼が低下 | コメント対応マニュアルを作成し、個別メッセージで丁寧に対応。公開コメントは一般的な案内に留める |
| 事実と異なる口コミが投稿される | 医療機関評価に影響 | 法的対応や削除依頼のルールを事前に策定。日本医師会の「苦情対応指針」を参考に対応フローを設定 |
法令・規制違反リスク
| リスク事例 | 内容 | 対策 |
| 医療広告ガイドライン違反 | 誇大広告、効果の断定、比較広告など | 厚労省ガイドラインを定期確認。投稿前に専門家(医療法務や薬事法務)によるチェック |
| 著作権侵害 | 他院や出版社の画像・動画を無断利用 | 使用権を明確にした画像・動画のみ使用。フリー素材や自作素材を活用 |
運用担当者に起因するリスク
| リスク事例 | 内容 | 対策 |
| SNS担当者の知識不足や判断ミス | 誤情報や個人情報漏えい、炎上など | 定期研修で医療情報の正しい発信方法、個人情報保護、クレーム対応を教育 |
| 担当者変更による運用混乱 | 投稿内容や対応の一貫性が失われる | 運用マニュアル、承認フロー、投稿カレンダーを整備し、担当者交代時も引き継ぎ可能に |
整形外科クリニックでのSNS運用におけるリスクは、個人情報漏えい・誤情報発信・炎上・法令違反・運用者ミスが主なものです。これらのリスクに対しては、以下の対策を組み合わせることが有効です。
・医療広告ガイドライン・個人情報保護法の遵守
・投稿前承認フローと運用マニュアルの整備
・ネガティブコメント対応ルールの策定
・定期的な担当者教育・研修
・公的情報や学会情報の引用で信頼性を担保
安全性と効果を両立させることで、SNSを患者さまとの信頼構築・集患施策として最大限活用できます。
SNS運用における評価基準と改善サイクル
SNS運用では、フォロワー数やエンゲージメント率、予約数などのKPIを設定し、定期的に分析することが重要です。Google AnalyticsやSNSのインサイト機能を活用することで、どの投稿が患者さまに響いたかを把握できます。
さらに、患者さまへのアンケートやSNSコメントを通じてフィードバックを収集し、改善策を立案・実行することで、運用の効果を高めることができます。ここでは、整形外科クリニックのSNS活用のためにおさえておきたいポイントを解説します。
KPI(重要業績評価指標)の設定
SNS運用におけるKPIは、クリニックの目的に応じて複数設定することが推奨されます。整形外科クリニックのSNS活用において、以下の指標が重要です。
| KPI | 内容 |
| フォロワー数・ページビュー | SNSアカウントやWebサイトの閲覧数 |
| エンゲージメント率 | いいね・コメント・シェアの割合 |
| 予約数・問い合わせ件数 | SNS経由での新規予約・問い合わせ |
| 患者さま満足度 | SNSやアンケートでの評価 |
データ収集による分析と評価
SNSの分析ツールやWeb解析ツールを活用することで、投稿の効果を定量的に把握できます。
SNSインサイト
・Instagram:リーチ数、保存数、シェア数、プロフィールクリック数
・X(旧Twitter):インプレッション、エンゲージメント、クリック数
・YouTube:再生回数、視聴維持率、チャンネル登録者増加数
・LINE公式:メッセージ開封率、友だち追加数
Google Analytics
・SNSからWebサイトへの流入数や予約ページの到達率
・診療予約フォームのコンバージョン率
アンケート調査
・来院患者さま向けにSNS経由で知ったかどうか確認
・患者さまの満足度や情報提供の理解度を収集
フィードバックを基にした投稿の評価
令和7年版情報通信白書では、スマートフォン・SNS・クラウドサービスの浸透拡大が「デジタル社会の基盤化」の一つとして位置づけられており、とくに「SNSを通じた情報流通とコミュニケーションの双方向化」が強調されています。この文脈を踏まえると、医療機関のSNS運用においては以下のようなポイントが重要となります。
・コメント・DM・リアクションなど、ユーザーからの質問・感想・反応を整理・集計し、どの投稿が効果的だったかを把握
・発信内容の正確性・透明性・信頼性を定期的にチェックする
・患者ニーズ・不安・疑問点を把握し、「次回投稿のテーマ」「投稿形式(動画・図解・テキスト)」「配信タイミング」などにフィードバックを活かす
・投稿後、定量的指標(例:いいね数、コメント数、CTR、DM問い合わせ数)と定性的指標(例:感想・質問内容の傾向)の2つの指標をもとに評価し、改善ポイントを明確にする
このように投稿の品質・ユーザーとの関係性・発信頻度・運用体制を整え続けることで、「単なる情報発信」から「コミュニケーション/信頼構築」の場へとSNSを転換できます。
【参考データ】
令和7年版 情報通信白書|総務省
改善サイクルの構築
効果測定結果をもとに、PDCAサイクルを回すことで投稿の内容や運用を最適化します。
Plan(計画)
投稿テーマや形式を改善案として設定
例:リハビリ動画の尺を短縮して視聴完了率向上を狙う
Do(実行)
改善案を投稿に反映
Check(評価)
KPIやアンケート結果を分析
どの投稿が予約や問い合わせにつながったかを確認
Action(改善)
成功例を標準化し、失敗例の原因を特定
他クリニックの事例(Instagramの症例動画で新規患者さま獲得など)を参考に応用
SNSの効果測定と改善は、数値指標(KPI)+患者さまの声(定性的フィードバック)を組み合わせて行うことが重要です。定期的なPDCAサイクルを回すことで、整形外科クリニックにおけるSNS運用は、患者さまとの信頼構築・集患効果の最大化につながります。
SNSを活用した整形外科クリニックの未来像

SNSはもはや単なる情報発信ツールではなく、地域医療におけるコミュニケーション基盤として、整形外科クリニックの経営戦略に不可欠な要素になりつつあります。
適切に運用すれば、集患・教育・専門性アピールを同時に実現できます。今後もSNS活用は、整形外科クリニック経営における必須戦略として位置付けられるでしょう。クリニック経営に有効なSNSを取り入れ、効率的な集患を実現しましょう。